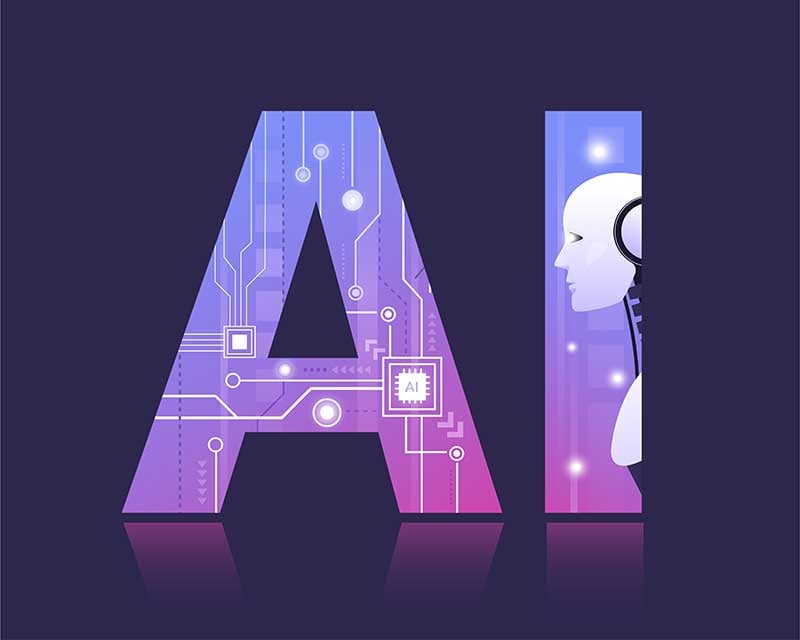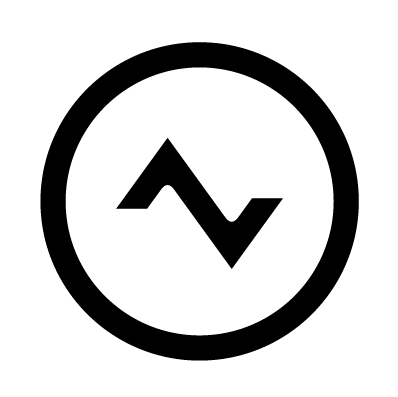生成AIとは
はじめに、生成AIに関する基礎知識を振り返っておきましょう。
学習データを活用して新たなコンテンツを生成できるAI
生成AI(ジェネレーティブAI)とは、学習データを活用して新たなコンテンツを生成できるAIのことです。具体的には、文章や画像・動画、楽曲、プログラムコードといったコンテンツを簡単な指示文(プロンプト)によって生成できます。ユーザーがAIに詳細なデータを与えなくても、オリジナルコンテンツを生成できる点が大きな特徴です。
生成AIに注目が集まっている大きな要因として、私たちが日常生活で使っている「自然言語」でAIに指示を出せるようになった点が挙げられます。プログラミング言語を使用することなく、人間同士が会話を交わすのと同じように気軽に活用できることが、世界中で注目を集めている大きな要因です。
生成AIに関する基礎知識やよく出てくる用語などはこちらの記事で詳しく説明しています。
AIと生成AIの違い
AI(人工知能)と一般的なプログラムとの大きな違いは、AIが「学習」する点にあります。あらかじめプログラムされたとおりの処理を繰り返すのではなく、学習を通じてアウトプットを改善し、よりユーザーニーズに即した使い方ができるようになる点がAIの特徴といえます。
生成AIは深層学習(ディープラーニング)によって進化したAIの一種です。AIは「強いAI(汎用型AI)」と「弱いAI(特化型AI)」の2種類に分類されます。現在、実用化されているAIはすべて弱いAIです。生成AIもまた「学習データにもとづいてコンテンツを生成する」という目的に特化されていることから、弱いAIに含まれます。
AIと生成AIの違いと成り立ちについての詳細は、下記の記事をご覧ください。
ChatGPTは生成AIの一種
ChatGPTは、OpenAIが開発した生成AIサービスです。プロンプト(文字や音声による指示)を通じて多彩なコンテンツを生成できます。具体的な活用例を見ていきましょう。
・リサーチ業務のサポート:テーマに沿った参考記事の抽出や要点のまとめ
・企画のアイデア出し:企画のアイデアを複数挙げ、採用するアイデアを絞り込む
・文書作成:テーマに沿った文書案の作成や文章校正
・イラスト制作:文字による指示を元に画像を生成・既存画像をアニメ風に変換
このように、従来は人が手作業で行う必要があった業務が、ChatGPTを活用することによってごく短時間で処理できてしまう点が大きなメリットです。
ChatGPTのサービスのしくみや、生成AIを利用した他のサービスについてはこちらの記事で解説しています。
生成AIの歴史
生成AIはここ数年で登場した技術のように思えるかもしれませんが、実はAIの研究そのものは1950年代から続けられてきました。生成AIへの理解を深めるには、生成AIがどのような経緯で進化してきたのかを知っておくことが大切です。
AI黎明期〜「冬の時代」へ
AIの研究が始まったきっかけとなったのは「人と会話ができる機械」というアイデアです。機械が「考える」とはどういうことかを定義するにあたり、「会話の相手が人間か機械か区別できない」状態になれば、機械が考えているといえるのではないか、と定義づけられました。
しかし、1980年代中頃までAIの研究は長らく停滞することになります。主な原因として挙げられるのは、当時コンピュータの処理能力がまだ低かったことや、研究に膨大な費用と時間を要していたことです。こうして、AI研究には長い「冬の時代」が訪れることになります。
ディープラーニング・自然言語処理技術の台頭
1980年代後半にニューラルネットワーク、2000年代にディープラーニング(深層学習)が登場したことにより、AIは複雑な処理を高精度で行えるようになりました。さらに、日本語や英語といった自然言語をコンピュータが扱うための「自然言語処理(NLP)」の技術が発展したことで、「人と会話ができる機械」のアイデアがようやく日の目を見ることになったのです。こうして生成AIは、プログラミング言語を扱わない一般ユーザーにとって身近なツールとなりました。
生成AIが急速に進化した要因
生成AIが急速に進化した背景には、「パラメーター数の急増」と「学習データの飛躍的な増加」という2つの要因があります。
パラメーター数はAIの学習の学習モデルの複雑さを表す指標です。ハードウェアの技術的な進歩やアルゴリズムの改良が、パラメーター数の飛躍的な増加に寄与しました。
また、インターネットの普及とSNSユーザーの増加は、AIが学習データとして活用できる情報量の飛躍的な増加をもたらしました。これにより、「AIの学習データをどのようにして用意するか」という重要な課題が解決されたのです。
生成AI開発の歴史から日常的に活用されるまでの詳細は下記記事をご覧ください。
生成AIの種類と活用法・想定されるリスク
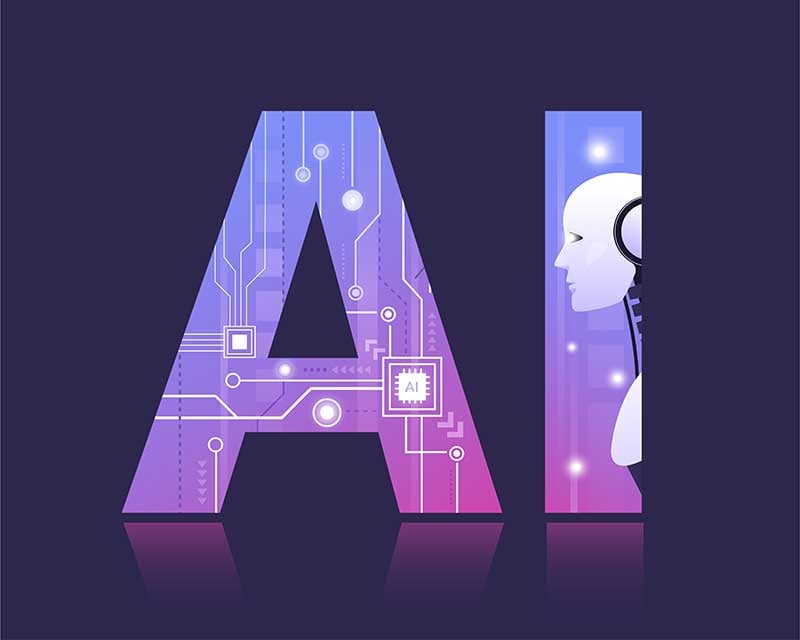
生成AIにはどのような種類があるのでしょうか。生成AIを効果的に活用するコツと、活用に伴って想定されるリスクを整理しておきましょう。
生成AIの主な種類
2000年生成AIの主な種類として、次の8点が挙げられます。
|
種類
|
概要
|
サービス例
|
|
1. 会話型
|
人間が使う言葉(自然言語)を用いて自然な会話ができる。
|
ChatGPT、Gemini、Copilot
|
|
2. 要約・校正型
|
文章の重要なポイントをまとめたり、既存の文章を読みやすく整えたりできる。
|
ELYZA LLM、要約AI Samaru、DeepL Write
|
|
3. 記事作成型
|
ユーザーが指定したテーマやキーワードに沿った文章を作成できる。
|
Transcope、SAKUBUN、Claude
|
|
4. 画像生成型
|
テキスト情報を元に画像を生成したり、元の画像を加工したりできる。
|
Adobe Firefly、Microsoft Designer、Stable Diffusion
|
|
5. 動画生成型
|
テキスト情報や画像から動画を生成できる。
|
Sora、Runway Gen-2、Make-a-Video
|
|
6. 音楽生成型
|
テキスト情報や希望のジャンルなどを元に、楽曲を制作できる。
|
MusicFX、Soundraw、Suno AI
|
|
7. コード生成型
|
プログラミングコードの作成をサポートする。
|
GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer
|
|
8. その他
|
多機能なタスク処理が可能なサービスや、テキスト情報を元に3Dモデルを生成できるサービス、無人受付システムを実現するサービスなど。
|
Notion AI、Poly、AIさくらさん
|
生成AIを利用した様々なサービスについて詳しくはこちらの記事で説明しています。
生成AIの活用に不可欠な「プロンプト」
生成AIを効果的に活用する上で重要なポイントとなるのが「プロンプト」です。プロンプトは生成AIのアウトプット(成果物)の質を大きく左右します。プロンプトを記述する際に意識しておきたいポイントは次の4点です。
1. 何をしてほしいのかを具体的に伝える
2. 制約条件を設ける
3. プロンプトを作り込みすぎない
4. 指示文を追加して回答の精度を高める
プロンプトの書き方や具体的な記述例については、次の記事で紹介していますので参考にしてください。
生成AIの活用に伴い想定されるリスク
生成AIを活用する際には、想定されるリスクを把握した上で対策を講じておくことが重要です。主なリスクと必要な対策として、次のものが挙げられます。
|
リスク
|
主な原因
|
講じるべき対策
|
|
機密情報の漏えい
|
プロンプトが学習データとして利用される場合があるため。
|
機密情報や個人情報をプロンプトに含めないようにする。
|
|
著作権などの侵害
|
生成されるアウトプットに著作物の一部が引用されていたり、特定のキャラクターや商標が含まれていたりする可能性があるため。
|
特定の作品やキャラクターなどを連想させる言葉をプロンプトに含めないようにする。除外する要素をあらかじめ指定する。
|
|
ハルシネーション
(幻覚)
|
学習データに誤情報や古い情報が含まれている可能性があるため。
|
生成AIによるアウトプットを必ず人の目で確認する。
|
下記の記事で、想定されるリスクと対策について詳しく説明しています。
Webメディア制作への活用例と注意点
生成AIはWebメディア制作にも活用できます。Webメディア制作に生成AIを活用するメリット・デメリットや、具体的な活用例と注意点は次のとおりです。
生成AIをWebメディア制作に活用するメリット・デメリット
【主なメリット】
・制作工程の省力化・効率化(例:記事構成の素案作成やリサーチの省力化)
・新たなアイデアの創出(例:記事企画やタイトル、見出し案のブラッシュアップ)
・外注費の削減(例:簡単なイラスト制作)
【主なデメリット】
・コンテンツの品質を安定させるのは容易ではない
・不正確な情報を発信するリスクがある
・情報漏えいが懸念される
デメリット面をカバーするには、人の目によるチェックを徹底したり、複数の生成AIを活用したりすることが重要です。また、アウトプットの情報源を必ず確認することや、生成AI活用のガイドラインを策定・周知することなども必要な対策といえるでしょう。
WEBメディア制作に生成AIを活用するにあたっては、下記の記事で詳細をご覧ください。
Webメディア制作に役立つ生成AIの活用例
具体的な5つの活用例を紹介します。
活用例1:「壁打ち」による企画立案のサポート
ターゲットとなる読者の立場を生成AIに担ってもらうことで、読者の課題や困り事を踏まえた回答を得られます。こうして得られたアイデアが企画立案に役立つでしょう。
活用例2:記事タイトルや見出し案の列挙
生成AIに複数の案を挙げてもらえば、よりよい表現を模索する際に活用できます。少人数のチームで制作を進める場合など、新たな着眼点を得たいときに効果的です。
活用例3:記事構成・本文の素案作成
生成AIが作成した構成や文章に肉付けしていくことで、質の高いコンテンツを制作できる確度が高まります。ターゲットや文字数を指定して素案を作成してもらうとよいでしょう。
活用例4:リサーチ業務の効率化
既存記事の傾向を箇条書きで挙げてもらうことで、競合メディアの動向を短時間でリサーチできます。資料などの要旨をまとめてもらい、大事な点を把握するといった活用方法も有効です。
活用例5:簡単なイラスト制作
簡易的なイラストを生成AIで制作したり、イラストレーターに発注する際のイメージ共有に役立てたりできます。
生成AIを実務で活用する際の注意点や特性を、こちらの記事で詳しく説明しています。
生成AIをWebメディアに活用する際の注意点
生成AIを活用する際には、いくつか注意しておきたい点があります。
プロンプトを適切に設定する必要がある
意図どおりのアウトプットを得られるかどうかは、プロンプト次第といっても過言ではありません。「要望は詳細かつ具体的に伝える」「AIに役割を与える」「制約条件を補足する」といった工夫を加えることによって、適切なプロンプトを設定することが重要です。
生成された内容が正しいとは限らない
生成AIの学習データには古い情報や偏った情報が含まれている可能性があります。成果物は必ず人の目でチェックし、精査することが大切です。
著作権侵害のリスクがある
前述のとおり、生成AIのアウトプットには著作物や既存のキャラクターなどの要素が含まれている可能性があります。特定の要素を除外する「ネガティブプロンプト」を活用するなど、著作権侵害のリスクを回避する工夫が求められるでしょう。
生成AIを特にWebメディア制作に活用したいとお考えの方は、下記の記事もご覧ください。
生成AIの強みを引き出す活用方法を見つけよう
生成AIの技術は日進月歩のため、今後も新たな機能や活用方法が次々と現れることが想定されます。生成AIの基本的な仕組みや開発の歴史への理解を深めることは、進化し続ける生成AIを使いこなしていく上で非常に重要なポイントです。この記事で紹介した活用のコツや注意点を参考に、生成AIの強みを引き出す活用方法を見つけていきましょう。