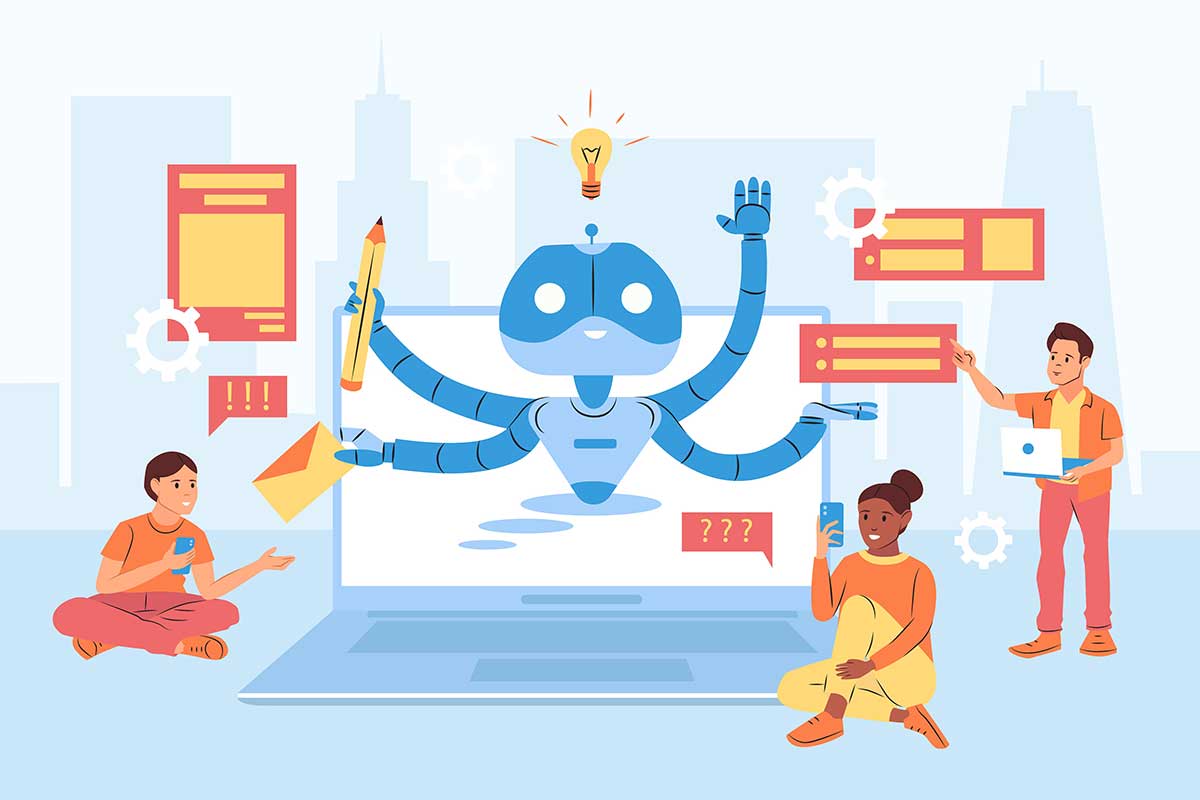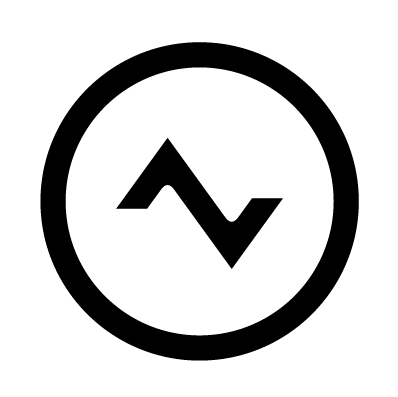生成AIをWebメディア制作に活用するメリット
生成AIを効果的に活用することで、さまざまなメリットを得られます。この点は、Webメディア制作においても同様です。生成AIをWebメディア制作に活用する主なメリットについて解説します。
メリット1:既存の業務を効率化・省力化できる
生成AIは既存業務の効率化・省力化に効果を発揮します。Webメディア制作であれば、次に挙げるような業務のサポートが可能です。
記事テーマに関するアイデアのブラッシュアップ
記事テーマに関するリサーチ(既存記事の取りまとめ・要約)
記事構成の素案作成
タイトルの候補出し
叩き台となる草稿の作成
原稿の誤字脱字チェック
記事に掲載する図やイラストの作成
いずれも従来は人手が必要な業務ばかりですが、生成AIを活用することでこれらの業務を効率化できます。制作チームの人数が限られている場合も、業務をスムーズに進めやすくなるでしょう。
メリット2:新たなアイデアの創出につながる
生成AIは新たなアイデアの創出にも役立ちます。生成AIを「壁打ち」の相手として活用することにより、多様な視点に立ったアイデアのヒントを得られるからです。
たとえば、「あなたはWebメディアの制作担当者です」といった指示を出すことで、生成AIに知識が豊富な制作メンバーと同じような役割を担ってもらえます。このほか、ターゲットとなる読者の立場から課題や困りごとを挙げてもらえば、読者ニーズを踏まえたアイデアの創出にも役立つでしょう。
メリット3:外注費を節減できる
生成AIの活用は、外注費の節減にもつながります。生成AIサービスによっては、テキストのほか画像や動画、音声などの生成にも対応可能です。たとえば、記事内に掲載するイラストや図解を生成してもらうといった活用方法が想定されます。
従来、Webメディアの制作工程には少なからず外注費がかかるものと考えられてきました。イラスト制作のように、これまでは外部委託が不可欠だった業務を生成AIに委ねることで、外注費を効果的に抑えられる可能性があります。
生成AIをWebメディア制作に活用する方法
ここからは、生成をWebメディア制作に活用する具体的な方法を見ていきましょう。プロンプト(指示文)の例と生成AIの回答をそれぞれ紹介していますので、プロンプト作成のヒントとしても活用してください。
(※本記事ではChatGPT 4o miniを用いた場合の回答を例に挙げています。)
例1:記事テーマのアイデアをブラッシュアップ
【プロンプト例】
あなたはWebメディア制作担当者です。次に挙げるテーマで「ワイヤレスイヤホン」に関する記事を制作したいと考えています。
・ワイヤレスイヤホンの特徴
・ワイヤレスイヤホンの種類
・ワイヤレスイヤホンの選び方
・ワイヤレスイヤホンと有線イヤホンの違い
・ワイヤレスイヤホンのメリット・デメリット
上記以外に読者が知りたいと考えている可能性のあるテーマを5つほど挙げてください。
【生成AIによる回答】
以下は、読者が「ワイヤレスイヤホン」に関して関心を持ちやすいと考えられる追加テーマを5つ挙げたものです。実際の検索ニーズやレビュー記事の傾向も踏まえて提案しています。
1. 人気ブランド・おすすめモデルの比較
読者は「どれを選べばよいかわからない」ことが多いため、価格帯別・用途別(通勤・運動・リモートワークなど)でのおすすめモデル紹介が有用です。
比較対象例:Apple(AirPods)/Sony/Anker/Bose/JBLなど。
2. ワイヤレスイヤホンの接続方式・技術(Bluetoothのバージョンなど)
「接続が不安定」「音飛びがする」といった不満が多いため、Bluetoothのバージョンやコーデック(SBC / AAC / aptX / LDACなど)の違いを解説する記事は読者の信頼を得やすいです。
3. バッテリーの持ちと充電方法の違い
通勤・旅行・長時間使用時の「再生時間」や「急速充電の有無」「ワイヤレス充電対応」などは、購入時の重要な比較ポイントです。
4. ノイズキャンセリングと外音取り込みの仕組みと違い
「ノイキャンって実際どうなの?」「外の音も聞こえるほうがいい?」といった疑問を持つ読者に向けて、仕組みや向いている使用シーンを解説できます。
5. 故障・紛失時の対応やサポート体制(保証期間・片耳紛失など)
実用面での不安を解消するために、「保証内容の比較」「片耳だけ失くした場合どうする?」といったトラブル対応の記事はニーズがあります。
プロンプトで挙げた5つのテーマ例とは異なる角度から、新たに5つの記事テーマが挙げられています。記事テーマのアイデア出しをする際、見落としていた視点を補ったり、新たな着想を得たりする上で役立つでしょう。
例2:記事構成やタイトルの素案作成
【プロンプト例】
挙げていただいた5つのテーマにて、記事構成とタイトルを提案してください。
【生成AIによる回答】
承知しました。以下に、先ほど挙げた5つのテーマそれぞれについて、タイトル案と**記事構成(見出しレベルでの構成案)**をご提案します。Webメディア記事として読みやすく、SEOも意識した構成にしています。
① 人気ブランド・おすすめモデルの比較
タイトル案:
「2025年最新版|ワイヤレスイヤホンおすすめ10選【価格・用途別に比較】」
記事構成:
1. はじめに:自分に合ったワイヤレスイヤホンの選び方とは?
2. ワイヤレスイヤホンの選定基準(音質・バッテリー・装着感など)
3. 用途別おすすめモデル(通勤・通学向け/スポーツ・アウトドア向け/在宅ワーク向け/ハイエンド志向向け)
4. 価格帯別おすすめモデル(5,000円未満・〜1万円・1万円以上)
5. 人気ブランドの特徴と比較表(Apple, Sony, Anker, Boseなど)
6. 購入前にチェックしたいポイント
7. まとめ
② 接続方式・技術(Bluetoothやコーデック)
タイトル案:
「Bluetoothって何が違うの?ワイヤレスイヤホンの通信規格・音質をやさしく解説」
記事構成:
1. はじめに:なぜ接続方式が重要なのか?
2. Bluetoothバージョンの違いと対応状況(4.2/5.0/5.3など)
3. コーデックの種類と音質の違い(SBC, AAC, aptX, LDACなど)
4. 遅延や音飛びを防ぐためのポイント
5. 対応機器(スマホやPC)との互換性に注意
6. まとめ:自分の環境に合った規格を選ぼう
③ バッテリーの持ちと充電方法の違い
タイトル案:
「バッテリー切れで困らない! ワイヤレスイヤホンの電池持ちと充電方式まとめ」
記事構成:
1. バッテリー性能が重要な理由
2. 再生時間の目安:本体 vs ケース込みの合計時間
3. 急速充電・ワイヤレス充電対応モデルの特徴
4. USB-C vs Lightning 端子の違いと今後の主流
5. モデル別バッテリー比較表(主要モデル)
6. 長持ちさせる充電のコツと注意点
7. まとめ:使い方に合った充電性能を選ぼう
④ ノイズキャンセリングと外音取り込み
タイトル案:
「ノイキャンだけじゃない! 外音取り込み機能との違いとおすすめモデル」
記事構成:
1. ノイズキャンセリングとは?仕組みと効果
2. 外音取り込みモードとは?どんな時に使う?
3. どっちが必要?シーン別に使い分けよう
4. ノイキャン&外音取り込み両対応モデルの紹介
5. 機能付きモデルの価格帯と性能差
6. 実際に使ってみた人の声(レビュー引用)
7. まとめ:日常のシーンに合った機能を選ぼう
⑤ 故障・紛失時の対応や保証制度
タイトル案:
「片耳なくしたらどうする?ワイヤレスイヤホンの保証とサポート完全ガイド」
記事構成:
1. 故障・紛失時にありがちなトラブルとは?
2. 主要メーカーの保証内容比較(Apple, Sony, Anker等)
3. 片耳だけ購入できる?修理対応の実情
4. 保証延長サービスやサブスク型保険の活用
5. 予備イヤホン・ケースの持ち方&保管の工夫
6. まとめ:購入時にサポート体制も要チェック!
例1で提示された5つの記事テーマについて、それぞれ記事のタイトルと構成が示されています。もちろん、提案を受けた記事テーマの中から「『3. バッテリーの持ちと充電方法の違い』の記事タイトルと構成を提案してください」のように指定することも可能です。このように、生成AIの回答をさらに深掘りする質問をしていくことで、アイデアの精度をさらに高める効果が期待できます。
例3:記事に掲載する図やイラストの作成
【プロンプト例】
あなたはWebメディア制作担当者です。ワイヤレスイヤホンに関する記事で、左右独立型イヤホンの片方を紛失して困っている若い男性の図を描きたいと考えています。イヤホンを片方なくしたことが視覚的に一目でわかる図を作成してください。
【生成AIによる回答】

プロンプトの内容を踏まえたイラストが作成されています。AIが生成したイラストを記事に掲載するほか、イラストレーターに依頼する際のイメージ共有に役立てることも可能です。
生成AIをWebメディア制作に活用する際の注意点
Webメディア制作に生成AIを導入するにあたって、いくつか注意しておきたい点があります。次に挙げる3点を念頭に置いて、生成AIを活用していくことが大切です。
生成されるコンテンツが正確とは限らない
生成AIによる回答は、必ずしも正確とは限りません。生成AIは学習データにもとづいてユーザーの質問を分析し、適切と推測される回答を導き出しています。よって、学習データにそもそも誤情報や古い情報が混在していれば、事実とは異なる出力結果が示されることにもなりかねません。
実際、生成AIが誤った情報をあたかも正しい情報かのように提示する「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象も確認されています。生成AIによって作成したコンテンツは必ず人の目でチェックし、事実関係や出典を確認しましょう。
著作権を侵害することのないよう留意する
生成AIが作成したコンテンツには、他人の著作物や創作物が無断で使用されているおそれがあります。生成されたコンテンツが著作権侵害に当たらないか、慎重に確認しなければなりません。
プロンプトを記述する際には、実在するキャラクターや作品を連想させる表現になっていないか、十分に留意する必要があります。必要に応じて除外すべき要素をあらかじめ指定しておくなど、著作権を侵害することのないよう細心の注意を払いましょう。
プロンプトが学習データに活用されるリスクを念頭に置く
生成AIの学習データには、ユーザーが入力したプロンプトも含まれている場合があります。プロンプトに機密情報や個人情報が含まれていた場合、無関係のユーザーにそれらの情報が提示される可能性も否定できません。
ネットワークに接続する必要がなく、単独で動作するタイプの生成AIサービスではない限り、入力したプロンプトがサービス提供事業者に送信されたり、AIの学習データとして活用されたりする可能性は十分にあります。プロンプトには重要な情報を含めないよう注意しましょう。
なお、ChatGPTなど一部のサービスでは、AIの学習機能をオフにする機能が提供されているものもあります。こうした機能を活用することで、情報漏えいのリスクを抑えるのもひとつの方法です。
生成AIを記事作成に活用するメリット
Webメディアの中でも生成AIを利用される具体的な事例として、コラムなど記事制作に生成AIを活用するケースを見ていきましょう。
メリット1:作業時間の短縮につながる
生成AIを活用することで、作業時間の短縮や業務効率化につながります。コンテンツを制作するにあたって欠かせないリサーチ業務や、記事構成づくりに生成AIを活用できるからです。
たとえば、記事のテーマやキーワードに関連する既存記事の一覧を生成AIで抽出したり、検索結果の上位に表示されている記事を要約したりできます。また、抽出・要約された記事を元に記事構成の素案を作成することも可能です。こうしたプロセスを生成AIに委ねることで、従来は人が担ってきた工程を省力化できます。
メリット2:新たな着想を得られる
生成AIはアイデア出しやブレーンストーミングにも活用できます。たとえば、記事タイトルや見出しのパターンを複数挙げてもらうことにより、アイデアをさらにブラッシュアップしたり、見落としていた観点がないかチェックしたりできるからです。
とくに少人数のチームや制作担当者が一人だけの場合、限られた時間内に挙げられるアイデアの数には限界があります。生成AIと「壁打ち」をすることで、新たな着想を得られる可能性は十分にあるでしょう。
メリット3:外注費を削減できる
生成AIの活用は、外注費の削減にも効果を発揮します。イラスト/画像制作や動画制作など、記事に掲載する素材を短時間かつ低コストで作成できるからです。
こうしたクリエイティブ制作には、従来多くの工程と費用を要していました。制作を外部委託する場合に費用がかかるのはもちろんのこと、社内で制作する際にも撮影や編集に少なからず準備が必要になるからです。生成AIであれば、テキストや類似画像などを元に短時間で画像や動画を生成できます。結果として、制作工程を大幅に削減できるでしょう。
生成AIを記事作成に活用する際の注意点
生成AIは記事制作の効率化に寄与するツールですが、活用するにあたって注意しておきたい面もあります。主な3つの注意点を確認しておきましょう。
注意点1:プロンプトを適切に設定する必要がある
生成AIによって作成される成果物の質は、プロンプトしだいで大きく変動します。プロンプトとは、生成AIに指示を与える際の「指示文」のことです。
前述のとおり、生成AIは「弱いAI」であることから、ユーザーが置かれている状況や要望の背景にある感情などをくみ取れません。こうした生成AIの弱点を補うには、プロンプトを記述する際に次のような工夫をする必要があります。
要望を詳細かつ具体的に伝える
AIに役割を与える(「あなたは税理士です」など)
制約条件を補足する(「200字以内で」「中学生にもわかるように」など)
想定どおりの成果物が得られない場合、プロンプトを調整したり、要望を付け加えたりしながら、ユーザーの意図を生成AIに伝えていくことになります。このように、生成AIを効果的に活用するには、適切なプロンプトを設定するスキルが求められる点に注意が必要です。
注意点2:生成された内容が正しいとは限らない
生成AIによるアウトプットが常に正しいとは限りません。学習データに誤情報や偏った情報、古い情報が含まれていれば、それらにもとづいて生成されたコンテンツも誤っている可能性があるからです。
よって、生成AIによる成果物は必ず人の目でチェックし、精査する必要があります。生成AIによるアウトプットをチェックすることなく、そのまま公開しないよう注意してください。一次情報を調査したり、事実確認を行ったりするプロセスが欠かせない点は、従来のメディア制作の工程と同様です。
注意点3:著作権侵害のリスクがある
生成AIの学習データに他人の著作物や制作物が含まれていた場合、著作権侵害のリスクがある点にも注意が必要です。たとえば、制作したいイラストのイメージが伝わりやすいよう、実在する作品名やキャラクター名をプロンプトに含めてしまうと、著作権侵害のリスクが高まる可能性があります。
著作権侵害のリスクを回避するには、ネガティブプロンプトを指定する方法もあります。ネガティブプロンプトとは、特定の要素を除外するために与える指示のことです。たとえば、「〇〇の要素を含めない」「〇〇に似ることのないように」といったように、具体的に指示を出すとよいでしょう。
Webメディア制作に生成AIを効果的に取り入れよう
今回紹介したとおり、Webメディア制作には生成AIを活用できる工程が数多くあります。既存業務の効率化や新たなアイデアの創出が可能になるなど、生成AIを活用するメリットは決して少なくありません。
一方で、生成AIによるコンテンツ制作には人の目によるチェックが欠かせないのが実情です。生成AIに頼り切るのではなく、活用する範囲や具体的な用途を決めておく必要があるでしょう。制作工程のうち、生成AIを取り入れられそうな業務について社内で検討してみてはいかがでしょうか。