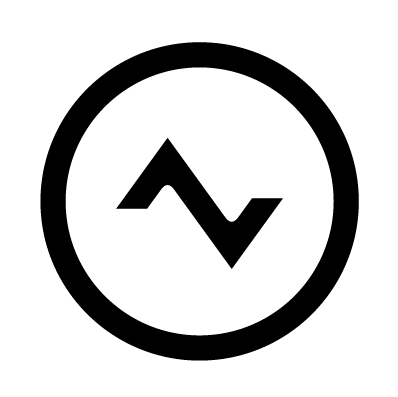生成AIをWebメディア制作に活用するメリット
生成AIをWebメディア制作に活用することで、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。Webメディア制作に特化したメリット3点を紹介します。
メリット1:制作工程の省力化・効率化につながる
ひとつめのメリットは、制作工程の省力化や効率化を実現できることです。コンテンツ制作に欠かせないリサーチや、記事構成の素案作成など、従来は人が携わる必要があった工程の一部を生成AIに委ねられます。
制作工程の省力化・効率化は制作期間の短縮につながるだけでなく、限られた人員で質の高いコンテンツを制作していくためにも重要なポイントです。多くの工程と作業を必要とするWebメディア制作を、よりスムーズに進められる可能性が高まります。
メリット2:新たなアイデアが創出される
新たなアイデアの創出に役立つことも、生成AIをWebメディア制作に取り入れるメリットのひとつです。記事企画やタイトル・見出し案を検討する際、生成AIにアイデアのブラッシュアップを依頼する「壁打ち」を行うことで、より考え抜かれた案を打ち出せる確率が高まります。
また、少人数の制作チームにおいては、ブレーンストーミングの一環として生成AIを活用する方法もあります。見落としていた視点を生成AIで補完することにより、より読者の視点に立ったコンテンツを作成しやすくなるでしょう。
メリット3:外注費を削減できる
生成AIの活用は、外注費の削減にも効果を発揮します。従来は外部委託が不可欠だった工程を生成AIによって代替することで、外注費が不要になったり、依頼する業務範囲をより限定したりできるからです。
たとえば、記事に掲載する簡単なイラストであれば、画像生成AIを活用して制作できる場合があります。修正依頼の回数にも制限がないため、納得できるまで成果物をブラッシュアップできる点も大きなメリットです。
生成AIをWebメディア制作に活用するデメリット
生成AIの活用はWebメディア制作上多くのメリットをもたらす一方で、使い方によってはデメリットとなり得る面もあります。とくに下記の3点に関しては、生成AIを制作工程に導入する際に注意しておく必要があるでしょう。
デメリット1:コンテンツの品質を安定させるのは容易でない
生成AIによるアウトプットを安定したものにするには、相応のスキルが必要です。成果物に求める条件が適切に指定されていない場合、既存記事を寄せ集めた一般的なコンテンツが生成されてしまうおそれがあります。また、LLM(大規模言語モデル)の多くは日本語に対応しているものの、不自然な言い回しや通常使われない表現が混在した文章が生成されるケースも見られるのが実情です。
こうした問題はプロンプトを調整することで回避できる場合もありますが、さまざまな記事の作成に対応できる汎用性の高いプロンプトを作成するには知識やスキルが不可欠です。生成AIの活用に精通した人材を育てていく必要があることも、大きな課題のひとつといえるでしょう。
デメリット2:不正確な情報を発信するリスクがある
生成モデルの学習データに誤情報や古いデータが含まれていた場合、生成されるコンテンツも不正確なものになってしまうおそれがあります。生成AIによるアウトプットの真偽については、人の目によるチェックが不可欠です。
また、生成AIが事実とは異なる情報を正しい情報であるかのように提示する「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象も確認されています。人の目によるチェックでは間違いを判別できなかった場合、フェイク情報が生成されるリスクがあることも、生成AIを導入するデメリットのひとつです。
デメリット3:情報漏えいが懸念される
生成AIを業務に活用することで、重要情報や個人情報の漏えいにつながることが懸念されます。生成AIサービスによっては、ユーザーが入力したプロンプトを学習データとして活用しているケースも少なくないからです。
プロンプトに自社が保有する重要情報や個人情報が含まれていた場合、無関係のユーザーに対してこれらの情報が表示される可能性があります。生成AIが学習する仕組みや、学習に用いられるデータの範囲を明確にした上で、ルールに則って活用していくことが大切です。
デメリットへの4つの対応策
ここまでに見てきたとおり、生成AIにはメリット・デメリットの両面があります。メリット面を効果的に引き出すには、次に挙げるようなデメリットへの対応策を講じておくことが重要です。
対応策1:人の目によるチェックを実施する
第一に講じるべき対策は、生成AIのアウトプットを必ず複数名で確認する体制を構築することです。生成AIによる成果物は正確性が保証されていないことを念頭に置き、「間違いがある」という前提に立って慎重に精査する必要があります。
成果物をチェックする際には、生成AI特有のウィークポイントを把握しておくことも大切です。たとえば、数値の単位や固有名詞、助詞の用法など、生成AIが正しく出力できないケースが散見されるパターンをリストアップし、重点的にチェックしていくとよいでしょう。
対応策2:複数の生成AIを活用する
単一の生成AIサービスを活用するのではなく、複数のサービスを併用するのも有効な対策といえます。生成AIサービスによって、採用されているLLMの種類やバージョン、学習の進捗状況などに差があるからです。
実際、ある生成AIサービスから得られたアウトプットと、別の生成AIサービスから得られたアウトプットが大きく異なるといったこともめずらしくありません。少なくとも2種類以上の生成AIサービスを活用し、アウトプットを比較する習慣を身につけましょう。
対応策3:情報源を必ず確認する
生成AIによるアウトプットに含まれる情報の真偽は、必ず一次情報を参照して確認することが大切です。出典を明示するようあらかじめプロンプトで指定しておき、提示された出典が適切な資料であるか確認することをおすすめします。
また、生成されたコンテンツに他人の著作物や創作物が使われていないか確認することも重要です。著作権を侵害することのないよう、特定の商標やキャラクターなどを連想させる単語をプロンプトに含めないようにする必要があります。成果物をチェックする際には、入力したプロンプトもあわせてチェックするとよいでしょう。
対応策4:生成AI活用のガイドラインを策定・周知する
生成AIの用途や利用範囲、利用時の注意点を明文化し、担当者に周知することも欠かせない対策といえます。担当者任せにするのではなく、生成AIをどの工程に活用するのか、どういった活用の仕方が禁止されているのか、具体例を交えてガイドラインを策定するのがポイントです。
生成AI活用に関するガイドラインどおりに運用されているか、定期的にチェックすることも大切です。生成AIは日進月歩のため、過去に定めたルールが実態にそぐわなくなることも想定されます。必要に応じてルールを見直し、変更点を都度周知しましょう。
Webメディア制作におすすめの生成AI活用例3選
Webメディア制作におすすめの生成AI活用例を紹介します。制作工程の効率化や、アイデアの創出につながる活用方法を検討する際に役立ててください。
活用例1:記事テーマや見出し案の列挙
記事テーマのアイデアや、タイトル・見出し案などを複数挙げてもらう活用方法が想定されます。とくに少人数の制作チームにおいては、限られたメンバーで創出できるアイデアの総量には限度があるからです。プロンプトで「あなたはマーケティング担当者です」「あなたは営業部の中間管理職です」といった役割を与えることで、読者の目線に立った課題や困りごとを踏まえた有益なアウトプットを得られるでしょう。
活用例2:記事作成に必要なリサーチの補助
記事作成に欠かせないリサーチの工程に関しても、生成AIを活用することで効率的に進められます。既存記事の傾向を箇条書きで挙げてもらうことで、競合メディアの動向を短時間でリサーチできるからです。
また、コンテンツ制作に向けて資料を読み込んでおく必要がある場合、生成AIに資料を要約してもらうことも可能です。資料の要旨を短時間で把握できるため、要点を押さえた企画案や記事構成などを作成できる可能性が高まります。
活用例3:簡単なイラスト制作
記事に掲載するイラストを、画像生成AIで作成する方法もあります。複雑な図や専門知識が求められる図解などを除けば、ごく簡単な指示文によってイラストの生成が可能です。
要望どおりのイラストが一度で生成されなかった場合、指示文を追加して修正してもらうこともできます。従来は外注していたイラスト制作をより低コストかつ短期間で制作できるため、制作工程に要する費用や期間の短縮につながるでしょう。
生成AIのメリット面を引き出す活用方法を検討しよう
生成AIは便利な活用方法や優れた機能などに注目が集まりがちですが、実務で活用する際にはデメリット面も十分に理解しておくことが大切です。デメリットへの対策を十分に講じつつ、生成AIのメリット面を引き出す活用方法を検討していきましょう。今回紹介した生成AIのメリット・デメリットや具体的な活用例を参考に、自社の業務への活用方法をぜひ検討してみてください。