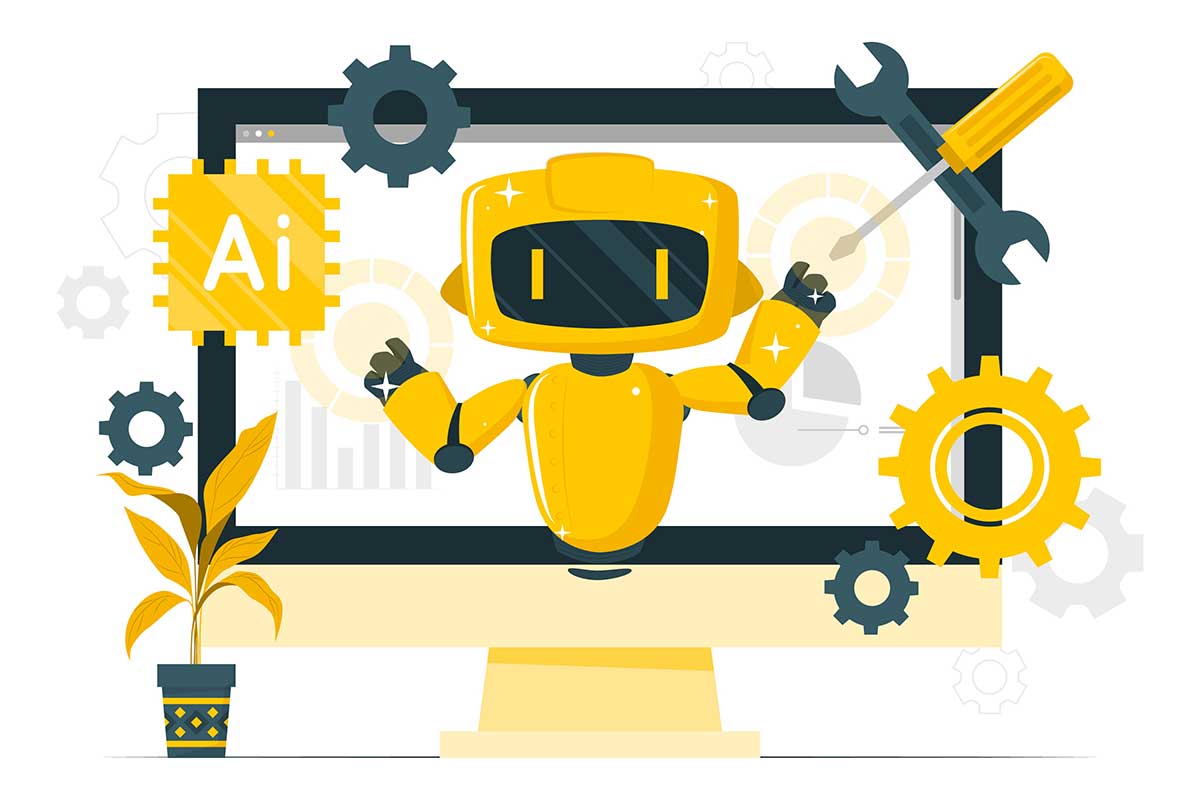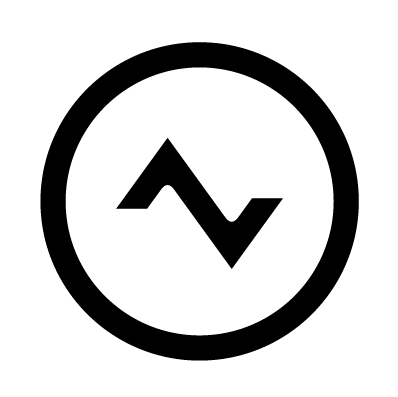生成AIは「弱いAI」
はじめに、そもそも現在使われているAIがどのようなものかを整理しておきましょう。
AIは大きく「強いAI」と「弱いAI」に分類されます。強いAIとは人間のように幅広い判断能力を備え、未知の状況にも柔軟に対応できる人工知能のことです。一方、弱いAIとは特定の用途において決められた範囲で処理を行うAIのことを指します。
生成AIはまるで人間のようにチャットのやり取りができたり、ユーザーの要望に応じてコンテンツを生成できたりするため、ともすると万能なツールのように錯覚しかねません。実際には、単語間の関係性を分析し、学習データにもとづいて最適な回答を導き出している「弱いAI」の一種です。生成AI自体が意思をもって考えたり、感情を伴う判断を下したりしているわけではありません。
生成AIにできること
生成AIの大きな特徴として、人間が使う言葉(自然言語)を介してやり取りができる点が挙げられます。従来型のAIの場合、希望する処理を実行するにはプログラミングの知識が不可欠でした。自然言語を使って次に挙げるような処理ができる点が、生成AIと従来型のAIとの大きな違いといえます。
テキスト生成
ChatGPTやWindows Copilotといった生成AIサービスは、テキスト生成に対応しています。LLM(大規模言語モデル)と呼ばれる生成モデルを用いて、大量のテキストデータを学習した上で、ユーザーの質問内容を分析したり、質問に応じた回答を生成したりできる点が特徴です。
たとえば、特定のテーマやキーワードについて解説する文章を生成したり、既存の文章を要約したりできます。「〇〇が△△する物語を作成してください」などの指示を与えることで、小説を執筆するといった処理にも対応可能です。
画像・動画生成
テキスト情報や画像データなどを元に、新たな画像や動画を生成できます。ユーザーが入力したテキストをテキストエンコーダが画像の内容を表す数字の列(ベクトル)へと変換し、さらに画像生成器がベクトルを画像へと変換するのが基本的な仕組みです。
一例として、「草原を子犬が2匹走っているイラストを描いて」といった指示を出すことで、数秒〜数分程度で要望に応じた画像が生成されます。画像や動画の制作工程を大幅に削減したり、制作期間を短縮したりする効果が期待できるでしょう。
音声生成
テキスト情報や短い音声データを元に、まるで実際に人が話しているかのようなリアルな音声を生成できます。実在する人物の声を元に、新たな音声コンテンツを制作することも可能です。
たとえば、FAQを読み上げることでカスタマーサポートに活用したり、創業者の録音音声を元に研修用の音声教材を制作したりできます。テキスト情報もしくは数秒程度の短い音声さえあれば、新たな音声コンテンツを作成できる点が大きな特徴です。
コード生成
実行したい処理を言葉で指示し、プログラミングコードを生成することも可能です。生成AIは自然言語処理(NLP)を用いて、人間の言葉を分析・処理する能力を備えています。そのため、ユーザーが希望する処理を通常の言葉で指示するだけで、処理に必要なコードをごく短時間で生成することが可能です。
生成AIが出力したコードをプログラマがコードの下書きとして活用したり、プログラミング初心者が学習のために活用したりすることも想定されます。あるいは、コードのデバッグをサポートするツールとして生成AIを利用することも可能です。
生成AIにはできないこと
生成AIは幅広いコンテンツ制作に活用できるものの、決して万能なツールではありません。生成AIが苦手とする処理の一例を紹介します。
自律的な判断や創造
生成AIは、いわゆる「0から1を生み出す」処理には対応できません。コンテンツを生成するには、大量の学習データとユーザーによる指示が不可欠だからです。
私たち人間は、ふとした時に思わぬアイデアがひらめいたり、明確な理由がないにもかかわらず「こうしたい」といった意志をもって判断を下したりすることがあります。生成AIは、このような自律的な判断や創造ができないのが実情です。別の見方をすると、生成AIを効果的に活用するにはユーザー側が明確に指示を出す必要があります。
人の感情や倫理観に対する理解
生成AIは学習データを分析した結果をアウトプットとして提示します。したがって、ユーザーがどう感じているか、倫理的に適切といえるか、といった判断ができません。感情が理解できないという点は、生成AIを活用する際に必ず押さえておきたいポイントです。
たとえば、あるイラストを描いてほしい場合、人間のイラストレーターに依頼するのであれば、依頼者の言葉のニュアンスを捉えたり、背景情報を踏まえたりすることで希望に応じた成果物を制作できるでしょう。一方、生成AIはこうした非定型的な処理ができません。よって、どのような成果物を求めているのかを詳細かつ具体的に指示することが重要です。
合理性にもとづかない判断・思考
生成AIは合理的とはいえない判断や思考には対応できません。私たち人間は常に合理的な考えにもとづいて行動するケースばかりではないため、時には不条理な判断をしたり、理屈では説明がつかない結論に至ったりすることがあります。一方で、こうした合理性を欠いているように思える判断・思考が、人の心を捉えることもめずらしくありません。
生成AIは、あくまでも既存の学習データにもとづいてコンテンツを生成しています。こうして生成されたコンテンツが、多くの人の感情に訴えかけるものになるとは限らない点に注意が必要です。
未知の状況への対応
生成AIは未知の状況に対して、柔軟に対応できない場合があります。この傾向がとくに顕著に表れるのが、最新情報を踏まえる必要がある成果物です。生成AIは学習データを元にアウトプットを生成するため、学習データの範囲外に当たる最新情報には対応できないケースも少なくありません。
ただし、生成AIによる分析のプロセスにインターネット検索を取り入れることで、最新情報への対応を可能にしたサービスも登場しています。生成AIを活用する際には、学習データの範囲やインターネット検索の活用状況などを確認しておく必要があるでしょう。
Webメディア制作に役立つ生成AIの活用例
Webメディア制作ご担当者様が実務に生成AIを取り入れることを想定した、効果的な活用例を紹介します。
(※本記事では、ChatGPT 4oを活用した場合の回答を例に挙げています。)
活用例1:「壁打ち」による企画立案のサポート
記事の企画を立案する際、生成AIを「壁打ち」の相手として活用できます。ターゲットとなる読者の立場を生成AIに担ってもらうことで、読者の課題や困り事を踏まえた回答を得られるからです。
【プロンプト例】
あなたはマーケティング担当者です。
既存のMA(マーケティングオートメーション)が抱えている課題として、想定されるものを5つ挙げてください。
【生成AIによる回答】
マーケティング担当者の立場から、既存のMA(マーケティングオートメーション)が抱える課題として想定されるものを5つ挙げます。
1. 運用の属人化
MAツールの設定・運用が特定の担当者に依存してしまい、担当者が離脱するとノウハウが失われる。
設計者以外が触れず、「ブラックボックス化」してしまうケースも多い。
2. セグメント精度の低さ
顧客データが適切に統合・クレンジングされておらず、セグメントやパーソナライズ施策が機能しない。
静的なセグメントしか作成できず、リアルタイムの行動に応じた対応が困難。
3. コンテンツ不足・最適化の遅れ
自動配信シナリオに使うコンテンツが足りない、または質が低く、エンゲージメントが上がらない。
A/BテストやPDCAが回っておらず、「一度作って終わり」になりがち。
4. 営業部門との連携不全
MAでスコアリングしたリードが営業に連携されない、または質が悪いと判断されて無視される。
「マーケと営業の壁」があり、ナーチャリングがうまく機能しない。
5. 成果の可視化・評価が困難
どの施策がどれだけの成果を生んでいるかが分かりにくく、ROI(投資対効果)が見えない。
分析機能を使いこなせておらず、現場の直感で改善が行われるケースも多い。
活用例2:記事タイトルや見出し案の列挙
記事タイトルや見出し案を検討する際、生成AIに複数の案を挙げてもらうことで、よりよい表現へのブラッシュアップに役立ちます。とくに少人数のチームで制作を進める場合、新たな着眼点を得る上で役立つでしょう。
【プロンプト例】
あなたはWebメディア制作担当者です。
「加湿器の選び方」に関する記事を作成するにあたって、SEOを考慮したタイトルと見出しの例を3パターン挙げてください。
【生成AIによる回答】
るか以下に「加湿器の選び方」に関するSEOを意識した記事のタイトルと見出し構成例を3パターンご提案します。検索ユーザーのニーズ(目的別・タイプ別・失敗回避など)を意識して構成しています。
■パターン1:初心者向け・包括型(広く浅くカバーする)
タイトル案:
【2025年最新版】加湿器の選び方ガイド|種類・機能・おすすめの使い方まで完全解説!
見出し構成:
1. 加湿器の必要性とは?乾燥によるリスクと効果
2. 加湿器の主な種類とそれぞれの特徴
3. 加湿方式別のメリット・デメリット(スチーム式、超音波式など)
4. 使用場所・目的別の加湿器の選び方
5. 買う前にチェックすべき5つのポイント
6. よくある失敗例とその回避策
7. 初心者におすすめの加湿器3選(2025年版)
■パターン2:比較検討型(購買前の検索意図に対応)
タイトル案:
スチーム式?超音波式?失敗しない加湿器の選び方と人気モデル比較
見出し構成:
1. 加湿器を選ぶ前に知っておきたい「加湿方式」の違い
2. スチーム式 vs 超音波式 vs 気化式|どれがあなたに合う?
3. 【目的別】おすすめの加湿器タイプ(赤ちゃん・子どもがいる家庭向け、花粉症・アレルギー対策、オフィス・寝室用など)
4. 人気モデル徹底比較(価格・機能・静音性・メンテナンス性)
5. 実際に使ってわかった!選ぶときの注意点
■パターン3:悩み解決・問題提起型(体験談・後悔ワードを活用)
タイトル案:
【後悔しない】加湿器選びで失敗しないための7つのチェックポイント
見出し構成:
1. よくある「加湿器選びの失敗」とその原因
2. なぜ自分に合わない加湿器を買ってしまうのか?
3. 使用目的と設置場所の明確化がカギ
4. 見落としがちな「加湿能力」と「対応畳数」
5. 手入れが面倒?メンテナンス性で選ぶポイント
6. 電気代・音・安全性も要チェック!
7. 編集部おすすめの「後悔しない」加湿器モデル5選
活用例3:記事構成・本文の素案作成
生成AIに記事構成や本文の素案を作成してもらうことも可能です。生成されたアウトプットに人の手で肉付けしていくことで、質の高いコンテンツを制作できる確度が高まります。
【プロンプト例】
あなたはWebメディア制作担当者です。個人事業主向けに確定申告の仕方を伝える記事を制作したいと考えています。開業1年目の個人事業主が不安に感じる点を意識した導入文を200字以内で作成してください。
【生成AIによる回答】
個人事業を始めたばかりの1年目。自由な働き方の一方で、「確定申告って何から始めればいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、開業1年目の個人事業主が知っておきたい確定申告の基本と、スムーズに申告を進めるためのポイントをわかりやすく解説します。
活用例4:記事内イラスト・画像の生成
記事作成に欠かせないリサーチの工程に関しても、生成AIを活用することで効率的に進められます。既存記事の傾向を箇条書きで挙げてもらうことで、競合メディアの動向を短時間でリサーチできるからです。
また、コンテンツ制作に向けて資料を読み込んでおく必要がある場合、生成AIに資料を要約してもらうことも可能です。資料の要旨を短時間で把握できるため、要点を押さえた企画案や記事構成などを作成できる可能性が高まります。
活用例3:簡単なイラスト制作
記事内にイラストや画像を掲載したい場合、画像生成AIに制作を代行してもらうことも可能です。簡易的なイラスト・画像であれば生成AIで完結できるケースもあるため、制作期間や外注費を削減できる可能性があります。また、複雑な図の制作をイラストレーターに外注する際には、生成AIが作成した図をイメージの共有に役立てるのもひとつの方法です。
【プロンプト例】
あなたはWebメディア制作担当者です。事務職向けの記事で、電話対応に追われて疲弊している若い男性の図を描きたいと考えています。男性が焦っていることが表情や様子からわかる図を作成してください。
【生成AIによる回答】

Webメディア制作に生成AIを活用する際の注意点
ここまでに紹介してきたとおり、Webメディア制作ではさまざまなシーンで生成AIを活用できます。生成AIを活用するにあたって、どのような点に注意しておく必要があるのでしょうか。主な3つの注意点をまとめました。
人の目によるチェックの工程を必ず設ける
生成AIによるアウトプットは、必ずしも正確性が保証されているわけではありません。学習データに不正確な情報が含まれていたり、古い情報を参照していたりする場合、生成されるコンテンツも適切ではない可能性があります。
また、成果物の倫理的な側面に関しては、必ず人の目でチェックしなければなりません。読者に不快感を与えるコンテンツになっていないか、著作権侵害につながるリスクはないかといった点を、複数名の目で確認することが大切です。
機密情報や個人情報をプロンプトに含めない
ユーザーが生成AIサービスに入力したプロンプトが、AIの学習データとして利用されている場合があります。無関係なユーザーに対して表示されるアウトプットに、自社が入力した情報が表示されてしまう可能性も否定できません。
機密情報や個人情報をプロンプトに含めることのないよう、生成AIの活用に関するガイドラインを策定し、社内に周知する必要があります。また、実務担当者が生成AIの基本的な仕組みを理解した上で、プロンプトとして使用すべきではない情報を把握しておくことが重要です。
生成AIを活用する業務の内容・範囲を明確に決めておく
Webメディア制作工程のうち、生成AIをどの部分に活用するのか、具体的な利用範囲を明確にしておくことも大切なポイントです。どの工程でどう活用するのか社内のガイドラインに明記した上で、担当者に共有しましょう。
なお、現状では生成AIにコンテンツ制作の全工程を委ねるのはあまり現実的とはいえません。従来どおり人の手で制作を進めるのが基本です。生成AIを活用する際には「制作を支援するためのツール」と位置付け、最終的な判断や品質チェックは担当者の方が責任をもって行うことが大切です。
生成AIができること・できないことを把握して効果的に活用しよう
生成AIは急速に進化しており、Webメディア制作に活用できるシーンも増えつつあります。一方で、生成AIはあくまでも制作をサポートするツールのひとつです。生成AIができること・できないことを把握した上で、強みを活かして活用していく必要があるでしょう。今回紹介した生成AIの特性や活用例を参考に、生成AIをWebメディア制作に取り入れてみてはいかがでしょうか。