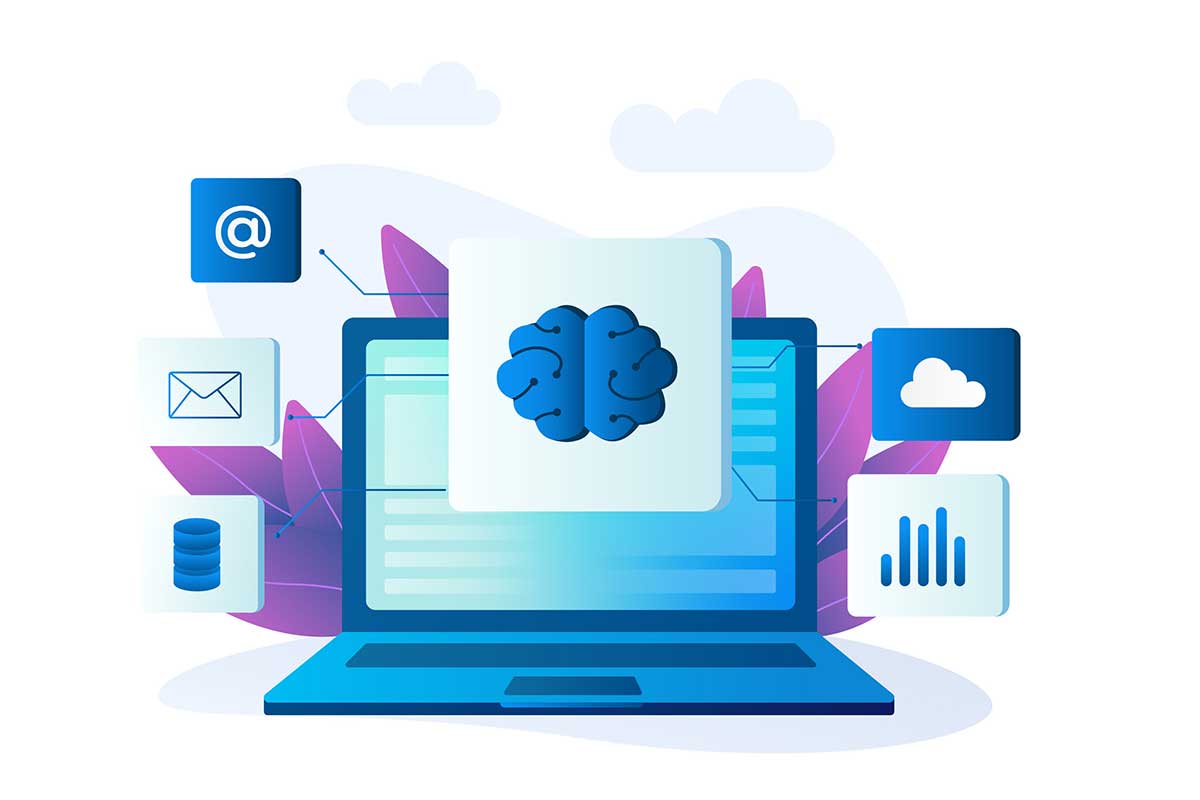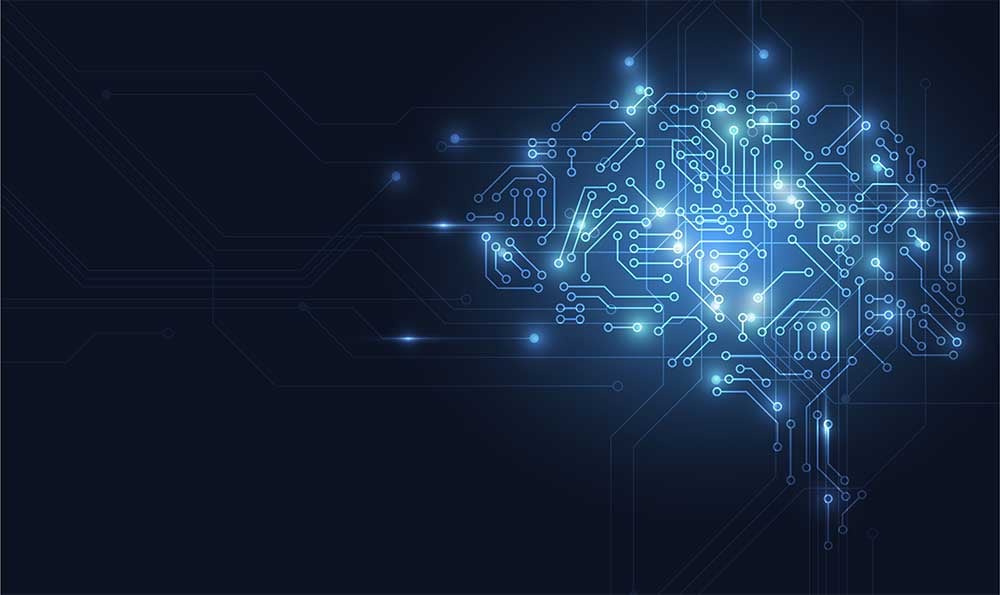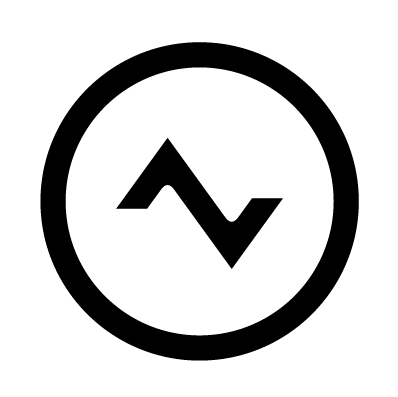AI黎明期
AIの歴史は1950年代までさかのぼります。AIの黎明期はどのような時代だったのか、ポイントを絞って見ていきましょう。
「人と会話ができる機械」という発想
AIの研究が始まったきっかけは、「人と会話ができる機械を開発する」という発想にありました。機械が人間のように「考える」とはどういうことかを定義するにあたって、「人と会話ができる」「会話の相手が人間か機械か見分けがつかない」ことを条件としたのです。
この定義は、イギリスの学者アラン・チューリングが提唱した「チューリングテスト」として広く知られることになります。考える機械を開発するにあたり、そもそも「考えること」や「知性」とは何を表しているのか? を再定義する必要があったのです。
チェスができるAIの研究
初期のAIは、チェスなどのゲームで人間と対戦するための能力を中心に開発が進められました。しかしながら、研究開発はなかなか順調には進みません。当時のコンピュータの処理能力で「考える機械」を実現するのは容易ではなかったからです。
この時代の状況を踏まえると、AIは「発想としては興味深いものの、実現は困難な技術」と考えられていたと捉えてよいでしょう。現代のAIにつながる発想自体はすでに存在していたにもかかわらず、技術的限界に阻まれ、発展途上の状況が続くことになります。
AI研究「冬の時代」の到来
AIに関する研究には「冬の時代」と呼ばれる時期が存在します。なぜAI研究が冷え込んでしまったのか、その背景を探っていきましょう。
AI研究に対する期待の冷え込み
1970〜1980年代に入っても、AIに関する研究は遅々として進みませんでした。当時のコンピュータでは処理に膨大な時間を要したり、期待する結果がうまく導き出されなかったりするケースが少なくなかったためです。結果として研究を続けるために必要な費用や時間が膨れ上がり、研究熱が冷え込む大きな要因となっていきます。この時期がAI研究において「冬の時代」と呼ばれているのは、AI研究に対する期待が萎みつつあったからです。
ニューラルネットワークの台頭
1980年代後半に入ると、「ニューラルネットワーク」と呼ばれる技術が登場しました。ニューラルネットワークとは、人間の神経回路を模した技術のことです。この技術が登場したことで、パターン認識や予測の精度向上がもたらされました。
一方で、AI研究には依然として大きな壁が立ちはだかっていたのが実情です。主な課題は、AIにインプットさせる学習データの不足でした。技術的には大量のデータを学習できるAIが開発できたとしても、その性能に見合う学習データをどのようにして用意するのか、という重要な問題が残されていたのです。
ディープラーニングの台頭から生成AIの登場へ
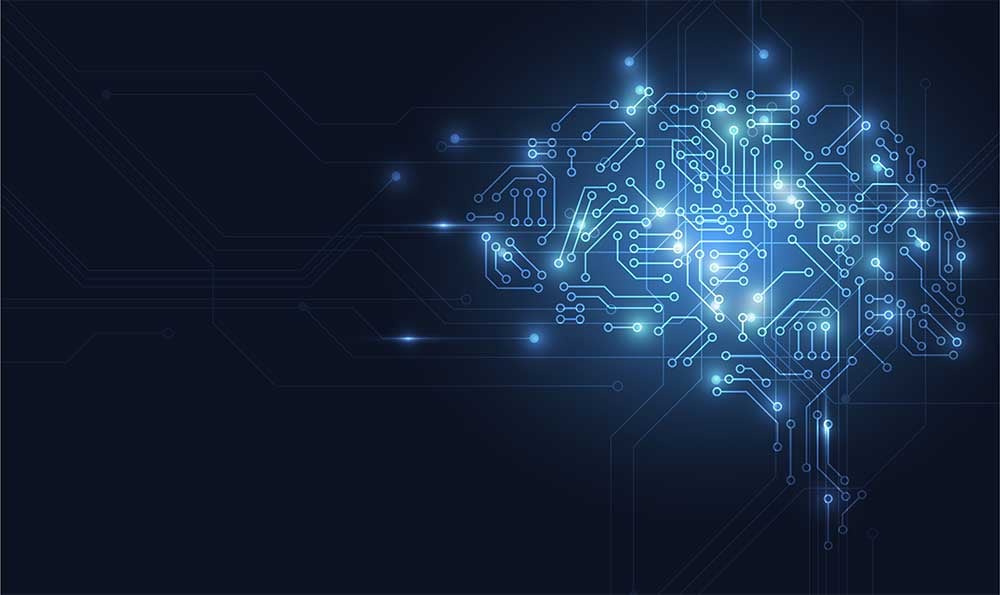
現代の生成AIにつながる重要な技術として「ディープラーニング」が挙げられます。ディープラーニングがAI研究にもたらした変化と、生成AIを身近なものにした「自然言語処理」について解説します。
ディープラーニングによる精度向上
2000年代には「「ディープラーニング(深層学習)」が登場しました。ディープラーニングは、ニューラルネットワークを多層化することによって大量のデータから特徴を抽出したり、パターンを学習したりする技術です。これにより、従来と比べて格段に複雑な処理を高い精度で行えるようになりました。
現在広く利用されつつある生成AIも、ディープラーニングを応用した技術のひとつです。文章や画像・動画、音声などを生成できるのは、ディープラーニングを駆使することで必要な情報をAIが自ら収集・蓄積できるようになったためです。このように、生成AIの台頭はニューラルネットワークからディープラーニングへと進化を遂げてきたAI研究の成果といえます。
自然言語処理の発展
生成AIが身近なものとなった大きな理由のひとつに、自然言語によるやり取りが可能になったことがあります。自然言語とは、私たちが日々使っている日本語や英語といった言語のことです。本来、コンピュータは自然言語が理解できません。生成AIと人間が言葉でやり取りできるのは、自然言語処理(NLP)と呼ばれる技術が進化したからです。
NLPは、文章を単語に分割する「形態素解析」、単語間の関係性を分析する「構文解析」、単語ごとの意味から文の意味を解釈する「意味解析」、文と文の関係性を解釈する「文脈解析」から構成されています。自然言語処理の発展によって、プログラミング言語を扱わない一般ユーザーであっても、人間との会話と同じ感覚で生成AIを利用できるようになったのです。
生成AIの急速な進化を後押ししした2つの要因
近年になって生成AIが急速に進化した要因として、「パラメーター数の急増」と「学習データの飛躍的な増加」の2つが挙げられます。
要因1:パラメーター数の急増
パラメーターは「変数」や「設定値」などを表す言葉です。パラメーター数は、AIの学習モデルの複雑さを表しています。ハードウェアの技術的進歩やアルゴリズムの改良によってパラメーター数を飛躍的に増やしたことが、生成AIの進歩を後押ししたのです。
パラメーター数の急増は、AI研究が長年抱えてきた技術的な問題の解決につながりました。処理に膨大な時間を要したり、計算コストが膨れ上がったりすることが、従来のAI研究において「壁」となっていました。AIの処理能力の向上は、生成AIに急速な進化をもたらした重要な背景といえます。
要因2:学習データの飛躍的な増加
もうひとつの重要な背景として、学習データの飛躍的な増加が挙げられます。インターネットの普及とSNSユーザー数の増加に伴い、日々膨大な量のデータが蓄積されるようになりました。これは、AIが学習データとして活用できる情報量が短期間のうちに急増したことを意味しています。
処理能力が極めて高いAIを開発した場合、学習データをどのように用意するのかが従来のAI研究における課題となっていました。インターネットの普及はこの問題を解決へと導き、生成AIの急速な進化をもたらしたのです。
AIの歴史を踏まえて、生成AIとどう向き合っていくべきか?
ここまで、AIから生成AIの台頭へとつながる歴史の大きな流れを見てきました。では、こうした歴史を踏まえて、私たちは生成AIとどう向き合っていけばよいのでしょうか。とくに意識しておきたいポイントは次の2点です。
AIは「突如として登場した技術」ではない
AI研究の歴史を知ると、AIが近年になって突然現れた技術ではないことがわかります。昨今は生成AIに注目が集まっているものの、70年ほどにわたって続けられてきた研究の成果であることを踏まえると、決して一過性のブームではないと捉えるのが自然でしょう。
今後も生成AIは進化を続け、私たちの暮らしに欠かせない技術のひとつになっていく可能性が高いと考えられます。生成AIを必要以上におそれて遠ざけるのではなく、有効活用していく方法を考えるほうが建設的です。
生成AIは「万能」とはいえない
生成AIの技術は急速に進歩しつつあるものの、決して万能なツールではありません。文章の生成や画像・動画の生成といったように、現状の生成AIは特定の用途に限って能力を発揮するツールだからです。このように、特定の処理に対応可能なAIを「特化型AI(弱いAI)」といいます。あらゆる状況に柔軟に対処できるAIは「汎用型AI(強いAI)」と呼ばれますが、生成AIをはじめ現時点で実用化されているAIはすべて特化型AIです。よって、生成AIが誤った情報や古い情報にもとづいて回答を生成する可能性も十分にあるのが実情です。
実際、生成AIが事実とは異なる情報を提示する「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象も少なからず確認されています。生成AIを活用する際には、人の目によるチェックが欠かせないことを十分に理解しておかなくてはなりません。生成AIを取り入れる業務内容や活用範囲を明確に定めるとともに、生成AIによるアウトプットは「間違っている場合がある」ことを前提に活用していく必要があります。
生成AIの研究開発の大きな流れをつかんでおこう
生成AIを活用する上で、その歴史的・技術的背景を知っておくことは非常に重要なポイントといえます。生成AIにはできること・できないことがある点を踏まえて、人が担うべき役割と生成AIに委ねる作業を明確に切り分けておかなくてはなりません。
今後、Webメディア制作にも生成AIが活用されるシーンが増えていく可能性があります。一方で、生成AIが学習データにもとづいてアウトプットを構築する仕組み自体は、今後も大きく変わらないでしょう。最新動向を踏まえたコンテンツや、正確な情報にもとづくコンテンツは、これからも人間の手で作っていくことになるはずです。生成AIの業務への活用を検討する際には、人間が担うべき役割に関してもあらためて話し合ってみてはいかがでしょうか。