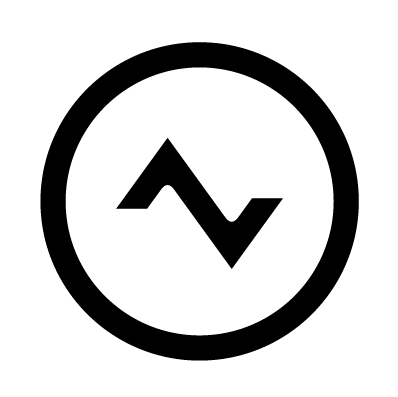今回のマーケティング関連のお薦め本:「営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60」
ターゲットを「顕在層」「準顕在層」「潜在層」に分類し、それぞれに対する施策とその順序を具体的に示したBtoBマーケティングのテクニック本。本書を「BtoBマーケター必読の書」と本書に太鼓判を押すのは、ネオマーケティングでBtoBマーケティングのコンサルティングサービスを立ち上げた加藤賢大です。
推薦図書「営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60」
<今回の推薦図書>
『営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60』(ブックダム)
著:田中龍之介
https://www.amazon.co.jp/dp/4911160020/
Instagram運用支援に参入した無名ベンチャーを、月平均5,000件の新規リードを獲得できる企業に成長させたマーケティング施策を全公開したのが本書。ターゲットを「顕在層」「準顕在層」「潜在層」に分類し、有効な施策を実施すべき順序とともに明確に解説します。再現性の高いその内容に、現場でリアルに役立つ「BtoBマーケティングの辞典」との評価も。
こんな方におすすめ
・初心者BtoBマーケターの教科書として
・中堅BtoBマーケターの振り返りとして
・BtoB企業向けにマーケティング支援をしている人
この本の紹介者

加藤 賢大
マーケティングリサーチャーとしてキャリアをスタートし、BtoB、BtoCを問わず戦略立案や施策実行を支援。自社マーケティングにおいても、戦略提案や業務提携、ウェビナー登壇やコラム執筆などを担当。その後、自社D2Cのブランドマネージャーを経て、現在は新規事業開発室の責任者としてクライアントのBtoBマーケに伴走。
BtoBマーケティングを理論的かつ美しく体系化した1冊
私が今回推薦するのは、『営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60』(ブックダム)です。
著者の田中龍之介氏は、Instagram運用支援を手がける株式会社SAKIYOMIの執行役員CMOで、BtoBマーケティング界隈では著名な方です。YouTubeなどを通じて積極的に情報発信しており、私も彼の動画をチャンネル登録して視聴していました。昨年の秋、動画で書籍の出版を知ったのが、本書を手に取ったきっかけです。
田中氏はまったくの未経験から、BtoBマーケティングを独学で学び、自分なりのマーケティング理論を確立しました。株式会社SAKIYOMIを無名のベンチャーから業界トップ企業へと導いた、その“勝ちパターン”の施策を本書で惜しげもなく公開しています。BtoBマーケターが「最初にこの1冊に出会っていれば、遠回りせずに済んだ」と感じるほど、実践的なノウハウが詰まっています。
私が読後にまず抱いたのは、「BtoBマーケティングをここまで理論的に整理し、美しく体系化してくれたことへの感謝」でした。特に、「潜在層(認知〜初期接触)」「準潜在層(興味・関心)」「顕在層(比較検討)」「商談」のファネル図とともに示した施策一覧は極めて秀逸です。
私自身もBtoBマーケティングの施策を独自に整理し、類似の図を自分で作成してクライアントへの提案に使っていました。本書を読んで、見過ごしていた点があったことに気づかされ、頭の中で整理できていたつもりでも、抜けや曖昧さが残っていたと感じました。
BtoBマーケティングをここまで具体的に解説した書籍は非常に稀です。著者の田中氏も、「マーケティングの成功事例は有名な大手企業だからこそできる大胆な施策が多く、今の『持たざる者』が明日から何をすれば良いのか、そのリアルで生々しいノウハウは中々表に出てこない」(p.18)と指摘しています。大手企業の成功事例をまとめた本はあるのですが、読者がそれをそのまま応用できるとは限らず、とくに、BtoBに関してはそれが顕著です。
長くマーケティングが活用されてきたBtoCの世界では、マーケティングのフレームワークはほぼ確立されています。また、広告施策などはかなりの規模感での投資が必要で、その施策を効率的に実施するノウハウを必要としている人は少なくありません。ビジネス的価値も大きい領域なので書籍も数多く出版されています。
これに対してBtoBマーケティングは、商材の単価は高くても市場規模が限定的で、ターゲットも限られます。営業主導での販路開拓や販売が重視され、「マーケティングは本当に必要なのか?」という認識が今も根強く残るのが現状です。そのため、この領域を対象にした書籍は少なく、だからこそ、本書は異彩を放つのです。
提示された「目標KPI」が施策の成果の目安にも
BtoB企業ではマーケティング専任者が配置されていないケースも多く、突然、マーケティングの担当になり、「何をすればよいのかわからない」という状況に陥るのも珍しくありません。戦略設計やターゲティングといった基本すら手探りの状態にある企業も多く存在します。本書は、そのような状況下にある企業にとって、非常に有用な実践書となるはずです。
というのも、冒頭でも触れたように、ターゲットを「潜在層」「準潜在層」「顕在層」「商談」と段階ごとに分け、それぞれに対してどのような施策をどのような順序で実施すればよいか、こと細かに解説しているからです。
しかも、株式会社SAKIYOMIが無名のベンチャーから業界トップになる成長過程で、どんな施策をどの程度の規模で行ったのかを詳細に記しているため、企業規模や事業フェーズに応じて参考にできます。
特に個人的に「これは役立つ」と思ったのは、どの施策についても、「今すぐ試して欲しい施策」と合わせて、「目標KPI」を示していることです。
例えば、潜在層向けの施策「SNS広告」であれば、
今すぐ試して欲しい施策
・CPAを下げる広告8パターンを実践する
目標KPI
・CPA3,000円〜6,000円(ホワイトペーパーの場合)
・目安の相場は月額15万〜30万円で、50〜100件のリード獲得
『営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60』p.73より
準顕在層向け施策「公式LINE」であれば、
今すぐ試して欲しい施策
・LINE追加時の特典の用意とリッチメニューの設定
・登録後1週間のステップ配信
・WEBサイト診断、SEO診断、SNSアカウント診断などの診断系コンテンツの提供
目標KPI
・開封率60〜70% 、CTR10〜20%
『営業してない相手から“契約したい”と言わせる マーケティングの全施策60』p.141より
といった具合です。
経験のある方もいるかもしれませんが、なにかしらの施策を実施して結果がデータとして出てきても、それがいったい高いのか低いのか、果たして効果があったのかどうか、実のところよくわからない、ということは少なくありません。本書で示された数値が一つの目安となり、施策の成果を確認することができます。
施策の優先順位と「BtoBマーケティングの民主化」
本書から「このタイミングならこの施策が効果的」「顕在層向けには、今、この施策を実施すればいい」など、新しい気づきを得ることができました。
その一つが、「優先順位」の重要性です。本書はマーケティング戦略の大きな考え方として、「受注に近い順に施策を進めるのが成功の鉄則」(p.29)と指摘しています。これは私も、クライアントに対して必ずと言ってもいいほどお伝えしていることです。
企業がもっとも求めているのは、「今すぐ買いたい!」と言ってくれる人です。当たり前のことではありますが、施策を検討している中で、いつしかこのことを見落としてしまいます。たとえば、「売上が上がらない」という課題があったとき、認知度に問題があると安易に考えて、一足飛びにCMを打とうか、交通広告を出そうかといった話になりがちです。
しかし、CMや交通広告は購入からもっとも遠い人へ向けた施策であり、CMを展開したからといって売上が右肩上がりになることはほぼありません。残念ながら限られた予算の無駄遣いになるだけです。「優先順位は受注に近い順」を意識することで、顕在層向けの地に足がついた施策に目が向きます。
また、「優先順位は受注に近い順」というのには、もう一つ理由があります。これも本書で指摘していることですが、それは、「マーケティングの予算を増やすこと」につながるからです。
「今後、マーケティングに注力していく」という社内方針はあれども、実績や前例がないため、「マーケティング担当部署は社内的に立場が弱い」ということがよくあります。予算をつけてほしい、投資をしてほしいと言っても社内的になかなか話がとおらない。前例がなく、売上にどの程度貢献するのかわからないことにお金は出せないと言われてしまうわけです。
しかし、本書が指摘するように受注に近い顕在層にフォーカスした施策を小さく始めて成果を出すことで、実績を作ることができます。すると、「マーケティングの成果がありましたよね。もう少し予算をかけて大きく取り組んでいきましょう」という話がしやすくなります。社内を動かすうえでも受注に近い層を優先するのは理にかなっているのです。
施策が成功することで、社内に「マーケティングのチカラ」を知らしめることができます。マーケターの存在価値が高まり、社員一人ひとりがマーケティングを考えるようになります。これを私は「BtoBマーケティングの民主化」と呼んでいます。これは、私がBtoBマーケティングに携わる中で、大切なコンセプトとしていることでもあります。
顕在層への鉄板アプローチ「LP×Web広告」
クライアントに「まずは顕在層からやっていきましょう」と提案するとき、“鉄板施策”となるのが、LP×Web広告です。「サービスサイト/LP改善」は、本書でも顕在層向けの施策で「最も費用対効果が合いやすい真っ先に取り組むべき施策」として紹介されています。
弊社でたとえるのであれば、「マーケティングリサーチ」をはじめ、「デジタルマーケティング」「PR」「コンテンツマーケティング」などさまざまなサービスがある中で、「マーケティングリサーチ」だけの専用ページを作り、Web広告や検索からLPに引っ張ってきて問い合わせにつなげるという施策です。
「リサーチ 比較 会社」といったキーワードで検索をする人はすでに、リサーチの実施に前向きで、どの会社がいいのかを検討している段階のはず。具体的な情報収集をしている時にたどり着いたLPにサービスの詳細があり、これを使えば課題が解決できるとなれば、問い合わせにつながりやすくなります。
ニーズのある人を確実に受注へとつなげていくのが、LP×Web広告を使った施策です。Web広告やLPはいずれも、比較的低予算かつ短期間での制作が可能で、小規模な施策から始めることができるのもメリットと言えます。
準顕在層を受注につなげるコンテンツ施策
また、新規リードは一定数獲得できているものの、そこから受注につながらないという相談も少なくありません。見込み顧客リストを保有しながら何もアクションを取らないのは、もったいなさすぎます。このようなケースでは、コンテンツを活用した施策をご提案します。ここでいう「コンテンツ」とは、記事やホワイトペーパー、動画などを指します。
再び弊社を例にご説明しましょう。
例えば、リストの中には、「リサーチに対して漠然とした関心はあるものの、現時点では問い合わせにまでは至らない」という層が存在します。このような見込み顧客に対して、ホワイトペーパーを提供し、ダウンロード用のリンクを設置することで、関心を具体的なアクションへとつなげる導線を構築するのです。
ホワイトペーパーには、その業界における共通の課題を明確に示し、読者に「これは自分が抱えている課題と同じだ」と共感できる内容を盛り込みます。その上で、解決策は複数存在するけれど、中でも「リサーチ」が最適である理由を具体的に示します。
すると、「自社の課題はリサーチによって解決できるかもしれない」と読者に感じてもらうことができます。弊社ではホワイトペーパーをダウンロードされた方には自動で御礼メールを送信し、その際、ホワイトペーパーのダウンロード用URLだけでなく、無料相談会やサービス資料請求ページなどへの案内もします。
「課題をお聞かせいただければ、それに最適なご提案を差し上げます」「ぜひお問い合わせください」「無料相談も承っております」といった導線を設けることで、商談へと誘導することができるのです。
このような流れを構築すれば、一律にテレアポを実施するよりも、顧客の関心度が高い状態で商談をスタートさせることができ、結果として受注に結びつきやすくなります。
コンテンツとして制作するのが、ホワイトペーパーなのか記事なのか、動画なのかは、商材などクライアント個別の状況に応じて判断します。ちなみに、本書でも「ホワイトペーパー」のほか、「成功事例集」「業界特化のノウハウ集」「最新データ集」といったコンテンツ施策が準顕在層向けの施策として挙げられています。
マーケティングはtoCもtoBも基本は同じ
このように、本書は私のようなBtoBマーケティングの現場に立って数年の中堅には有意義なふりかえりとなり、初心者には“教科書”として使える1冊です。実際、リサーチ部門から異動してきてBtoBマーケティングの知識が浅い若手メンバーに対しは、まず本書を読むよう薦めています。彼らにしてみたら、本書が施策の根拠や裏づけとなり、自信をもってクライアントに提案できるようです。
一方で、BtoBマーケティングを特別なものとして捉える必要はないとも考えています。BtoBだからこそのマーケティングの難しさは確かに存在します。よく言われるのは、BtoCのターゲットとなる一般生活者は個人で購買の判断を含め、物事を自分一人で決めるけれど、BtoBは、購買を決める人・使う人・お金を出す人がそれぞれ存在して、意思決定構造が複雑なため、マーケティングの難易度が高いということです。
それは確かなのですが、マーケティングはtoCであれtoBであれ基本的には変わりません。重要なのはターゲットを定めて、何をどう訴求していくか。ビジネスモデルや目標、現状とのギャップを踏まえて施策を考えていく、その思考経路は同じです。
本書は著者が指摘するように、BtoBマーケターにとって“武器”となる1冊であることは間違いありません。でも、BtoBマーケティングを学びたい、あるいは学ばなくてはならなくなった人に対しては、「そんなに構えなくても大丈夫」とお伝えしたいと思います。我々のようなプロに頼ってもいい。目的はスピード感をもった事業の成長です。そのために必要な優先順位は何かをまず、考えることが必要なのだと思います。
加藤 賢大に相談する