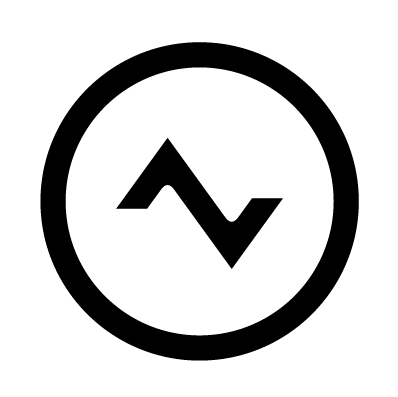新商品の企画やマーケティング戦略の構築をする際には、事前に市場調査を実施しておくことが重要です。市場調査にはさまざまな手法がありますが、消費者のリアルな実態を把握するには定性調査を取り入れることをおすすめします。
この記事では、市場調査に活用される定性調査の手法や、市場調査に定性調査を取り入れるメリットについてわかりやすく解説しています。定性調査を実施する際の注意点や、調査を進める手順もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
市場調査とは
はじめに、市場調査を実施する目的と調査方法の種類について、基本事項を整理しておきましょう。
マーケティングや戦略策定のために実施するリサーチのこと
市場調査とは、マーケティングや戦略策定に向けて実施するリサーチのことを指します。最新のニーズやトレンドを把握し、スピーディーな仮説検証や意思決定につなげることが主な目的です。
市場調査を実施することなくマーケティング施策や事業戦略を策定した場合、実態にそぐわない施策/戦略を実行してしまうおそれがあります。市場は常に変化しており、過去に効果を発揮した戦略や施策が現在も有効とは限りません。市場や消費者ニーズの実態を把握し、効果の高い施策を講じるためにも、市場調査は欠かせないプロセスといえます。
市場調査の種類
市場調査の手法には、大きく分けて「定量調査」と「定性調査」の2種類があります。
定量調査とは、数値化されたデータを収集するための調査手法のことです。回答数が多い/少ない、割合が高い/低いといった数値データを得られるため、全体の傾向を把握したい場合や、過去の調査データと比較したい場合に適しています。
定性調査とは、数値化できない心理や行動背景、価値観といった情報を収集するための調査手法です。対象者のインサイト(内面)を深掘りしたい場合に適しています。
市場調査に活用される定性調査の手法
市場調査に活用される定性調査の手法には、「グループインタビュー」「デプスインタビュー」「オンラインインタビュー」「エスノグラフィー(行動観察調査)」などがあります。各手法の実施方法やメリット・デメリット、実施する目的について、ポイントを押さえておきましょう。
グループインタビュー
複数の対象者(通常5〜8名)を一室に集め、座談会形式で実施するインタビュー調査です。一度に複数名の意見を聴取できるため、効率良く調査を進められます。また、他の回答者の意見に触発されて議論が深まったり、意見交換が活発に行われたりする可能性があります。
一方で、他の回答者には知られたくないデリケートなテーマには適さない点に注意が必要です。
【グループインタビューが適しているケース】
・商品・サービスの使用実態を把握したい
・商品改善に向けた意見・感想を聴取したい
・新商品開発のために消費者理解を深めたい
デプスインタビュー
対象者と1対1で実施するインタビュー調査です。一人の対象者からじっくりと意見・感想を聴取できるため、本音を引き出しやすい調査手法といえます。また、他人にはあまり知られたくないデリケートなテーマについて調査したい場合にも適した手法です。
ただし、1名ずつ調査を実施するため、時間がかかるという難点があります。また、インタビュアーの力量によって引き出せる情報量に差が生じやすい点や、調査結果を効果的に活用する難度が高いといった点がデメリットです。
【デプスインタビューが適しているケース】
・対象者のインサイトを深掘りしたい
・仮説を検証したい
・新たな着想を得たい
オンラインインタビュー
ビデオ会議ツールを活用して実施するインタビュー調査です。会場を準備する必要がなく、対象者は自宅などからインタビューに応じられるため、調査に協力する際のハードルを下げられます。一方で、実際に商品を手に取ってもらう・香りをかいでもらうといったインタビューは実施できません。また、理屈上はビデオ会議ツールの参加上限数まで対象者を招集できるものの、実際は人数が多すぎると会話がしにくくなる点に注意が必要です。
【オンラインインタビューが適しているケース】
・外出が困難な対象者(子育て中の方など)が含まれていることが想定される
・居住地を限定せずに実施可能
・商品を手に取る・香りをかぐといった工程が不要
エスノグラフィー(行動観察調査)
対象者の行動や生活を観察することで無意識に行なっている行動からインサイトの種を探索します。対象者が実際に生活している中でサービスや商品を利用している姿を確認できたり、ライフスタイルなども含む多彩な情報を得られます。ただし、調査には一定期間を要することから、多くの対象者に調査を実施するのは現実的ではありません。
【エスノグラフィーが適しているケース】
・新商品のコンセプト開発に役立てたい
・対象者のありのままの生活実態を知りたい
市場調査を定性調査で行う3つのメリット

前述のとおり、市場調査には定量調査と定性調査の2つの手法があります。定性調査を取り入れることで、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。
メリット1:数値化できない要素を把握できる
定量調査によって数値化されたデータを収集できるものの、なぜその結果が出ているのかを把握するのは容易ではありません。数値データの背景にある感情や動機を深掘りできることは、定性調査を取り入れるメリットといえます。
例えば、ある商品を「人にすすめたい」といった回答を得られた場合、すすめたい理由は回答者ごとに異なるはずです。商品のどのような点が気に入っているのか、より具体的に把握するには定性調査を行う必要があります。
メリット2:顧客や消費者の生の声を収集できる
定性調査では対象者の回答を「言葉」で記録します。これにより、意見や感想のニュアンスを含めて確認・共有できる点が大きなメリットです。市場調査においても、定性調査を通じて得られた対象者の声は加工せずそのままレポートに掲載することをおすすめします。自社側の解釈を加えないほうが、よりリアルな意見・感想を共有できるからです。
例えば、対象者が「はじめは自分に合わないと思ったけれども、友人が使っているのを見て買うことにした」と答えたとします。回答を端的にまとめると「友人の影響」が購入の直接的な動機です。しかしながら、「はじめは自分に合わないと思った」という部分にも重要なヒントが隠されている可能性があります。こうした微妙なニュアンスも含めて記録に残せる点が大きなメリットです。
メリット3:対象者の興味関心に応じて深掘りした質問ができる
対象者の回答内容に合わせて、臨機応変に質問できることも定性調査の大きなメリットのひとつです。意見や感想を深掘りして聞いていく中で、より実践的な解決策を得られる可能性があります。
例えば、調査対象の商品について「また購入したいかどうか」を尋ねたとします。「また購入したい」と答えた対象者がなぜそう感じるのか、個人的な理由や感情をより詳しく質問することも可能です。対象者が「他に良いと思う商品がないから」といった理由を挙げたとすれば、なぜ他社商品が良いと思わないのか聞いてみる意義があるでしょう。このように、対象者一人ひとりの状況に応じて質問を追加できることは、定性調査ならではの強みといえます。
定性調査を実施する際の注意点
市場調査に定性調査を取り入れる際の注意点を紹介します。定性調査のメリット面を最大限に引き出すためにも、次の3点を実践していくことが大切です。
自社の課題を整理し、仮設を立てておく
定性調査を行うにあたって、あらかじめ自社が抱えている課題を整理しておく必要があります。漠然と定性調査を始めても、何を明らかにしたいのかが定まっていなければ必要な情報を収集できません。まずは解決すべき課題を明確にすることが重要です。
その上で、自社商品の強みや魅力、競合他社と比較した場合の特長などを再確認しましょう。自社の得意分野やすでに保有しているノウハウなどを活かすことで、課題の着実な解決につながる可能性が高まるからです。課題解決に向けて有効な方策について仮説を立てた状態で、定性調査に臨むのが基本と捉えてください。
収集するデータの信頼性を重視する
定性調査の成否は、収集するデータの信頼性にかかっているといっても過言ではありません。偏った意見や感想が多勢を占めていたり、よく考えずに回答する対象者が散見されたりするようでは、市場や消費者ニーズの実態を見誤ってしまうおそれがあります。
信頼性の高い情報を収集するには、十分なサンプル数を確保すると同時に、質の高い回答を得ることが重要です。ターゲットの条件に合致する対象者を選定することに加え、対象者の本音を引き出す質問例をあらかじめ用意しておく必要があります。
調査結果をまとめる際に独自の解釈を加えない
調査後に結果レポートを作成する際には、対象者の発言に独自の解釈を加えないようにしましょう。回答はできるだけ加工していない状態で記載し、ニュアンスや言い回しも含めて共有できるレポートに仕上げるのがポイントです。
実際、わずかな言い換えや表現の変更であっても、担当者の先入観や願望が混入してしまうケースは少なくありません。例えば、調査の際には「(商品が)以前から気になっていた」という回答を得たにもかかわらず、レポートに記載する際に「以前から購入を検討していた」と言い換えた場合、意味合いが大きく変わってしまいます。このように、回答の趣旨が変化しかねない表現の変更や言い換えを避けることが大切です。
定性調査を進める手順
定性調査を進める際の具体的な手順を紹介します。
1. 調査の目的を定める
はじめに、調査を実施する目的を明確にします。自社が抱えている課題を整理した上で、調査を通じて何を明らかにしたいのかを社内で共有しておくことが大切です。
調査目的によって、収集すべきデータや必要な設問内容が大きく変わります。例えば、新商品開発に向けたアイデア出しのヒントを得たい場合と、既存商品の改善すべき点を知りたい場合とでは、対象者に投げかける問いは大きく異なるでしょう。目的が曖昧なまま調査を進めてしまうことのないよう注意が必要です。
2. 目的に合った調査方法を選ぶ
次に、調査目的に合った調査方法を検討します。調査対象や予算に応じて、適した調査方法を選定することが大切です。
前述のとおり、市場調査の手法には大きく分けて定量調査と定性調査の2つがあります。量的な情報を得たいのか、質的な情報を得たいのかによって、どちらの調査手法が適しているかを検討しましょう。調査目的によっては、両者を組み合わせて実施したほうが効果的な場合もあります。ポイントは、対象者のインサイトをどの程度深く探りたいのか、という部分です。例えば、商品に対する好印象の度合いが判明すればよいのであれば定量調査、なぜ好印象を抱いているのか、理由や背景も含めて分析したい場合は定性調査が適しています。
3. 質問項目を決定する
調査方法が決定したら、具体的な質問項目を検討していきます。定性調査といっても、唐突に「商品についてどう思いますか?」と尋ねても、対象者はどう答えればよいのか戸惑ってしまうでしょう。まずは選択式で答えられる質問を投げかけ、その回答を深掘りする質問を重ねていくのが得策です。
4. 市場調査を実施する
調査計画に沿って調査を実施します。定性調査では対象者の回答内容によって臨機応変に質問を投げかける必要があるため、インタビュアーのスキルによって引き出せる回答に差が生じがちです。事前にロールプレイングを実施し、調査目的の達成に役立つ質問の仕方や、回答を深掘りする度合いについて共通認識を形成しておく必要があります。
調査に必要なリソースを自社で確保するのが難しい場合は、外部の調査会社に依頼するのもひとつの方法です。その際には、調査の実施だけでなく調査の企画・設計や事後の分析、結果レポートの作成なども一貫して依頼できる調査会社を選ぶとよいでしょう。
5. 結果を分析し、レポートにまとめる
調査結果を分析し、レポートにまとめていきます。分析結果レポートは目的に応じて使い分けられるよう、サマリーレポート(概要版)とフルレポート(詳細版)の2種類を作成しておくのが得策です。
市場調査を実施する目的は、最新のニーズやトレンドの把握にあります。この点を念頭に置き、必要な情報を見やすくまとめるのがポイントです。定性調査のまとめ方や分析手法、レポート作成の手順については次の記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
定性調査を市場調査に役立てよう
市場調査に定性調査の手法を取り入れることで、対象者の心理や行動背景、価値観などをより深く分析しやすくなります。一方で、定性調査を効果的に実施するには専門的な知見やノウハウが欠かせません。自社で定性調査を実施するのが難しい場合は、外部の調査会社を活用することも視野に入れて検討することをおすすめします。
ネオマーケティングでは、今回紹介した定性調査の主な手法をいずれも実施可能です。調査の企画や設計、事後の分析、結果分析レポートの作成まで一貫してサポートしています。市場調査の実施を検討中の事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。