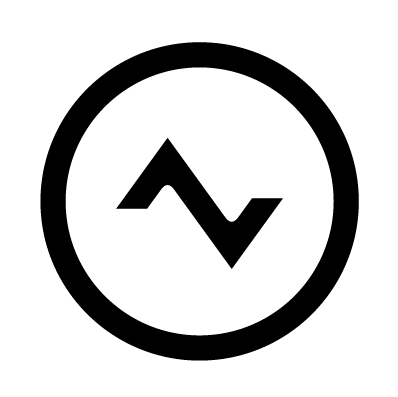定性調査を実施した後は、調査結果を分析した上でレポートとしてまとめることになります。調査を通じて多くの情報が集まったものの、それらをどのように整理すればよいのか迷ってしまうケースは多いのではないでしょうか。
この記事では、定性調査の結果をまとめる際の基本的な流れや、主な分析手法についてわかりやすく解説しています。レポートを作成にあたって注意しておきたい点や、定性調査結果の具体的な活用方法にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。
定性調査の結果をまとめる際の基本的な流れ
定性調査とは、数値では表せない心理や行動背景を詳細にヒアリングするための調査手法のことです。収集される調査結果は「(回答数が)多い/少ない」「(割合が)高い/低い」といった数値データではなく、調査対象者が実際に話した意見や感想となります。これらの結果をまとめる際の基本的な流れは次のとおりです。
1.発言録(発言内容一覧)を作成する
はじめに着手すべきことは、発言録の作成です。発言録とは、インタビューの内容を時系列で文字に書き起こしたもののことを指します。
発言録を作成する際には、調査対象者が実際に発した言葉をできるだけ加工せず、そのまま記載するのがポイントです。発言録をまとめる担当者自身の判断で発言内容を要約してしまうと、独自の解釈が加わることになりかねません。必要に応じて文を整える場合も、発言の趣旨やニュアンスが変化することのないように注意する必要があります。
2. 発言のピックアップとグルーピングを行う
発言録がまとまったら、その中からポイントとなる発言を抽出していきます。類似する表現や関わりの深い発言をグループ別にまとめ、見やすく整理しましょう。
発言をグルーピングする際は、大きな括りで分類するよう意識してください。この段階で細かくグループ分けをしてしまうと、担当者の解釈で発言を選り分けることにもなりかねないからです。例えば「好意的なコメント」「類似性が高い表現」のように、大まかな傾向を把握しておくのがポイントです。
3. 分析結果レポートを作成する
グルーピングされた回答を元に、分析結果レポートを作成します。グループインタビューの場合はグループごとに、デプスインタビューの場合は個々の対象者のインサイトを把握できるようにまとめるのがポイントです。
分析結果レポートに関しても、調査対象者の発言はできるだけ加工していない状態で記載しましょう。発言内容を要約したり、表現を変えたりすることで、ニュアンスが変化する可能性があるからです。
定性調査の主な分析手法
定性調査の結果を分析する際に用いられる手法には、いくつかの種類があります。ここでは、代表的な手法として「コーディング」「KJ法」「KA法」「上位下位関係分析」について見ていきましょう。
コーディング
コーディングとは、インタビュー内容をカテゴリーに分類し、コードを割り当てる分析手法のことです。コードによってデータが構造化されるため、情報を体系的に把握しやすくなります。発言内容の関連付けや比較をしたい場合に適した手法です。
【コードの振り分け例】
|
発言内容
|
コードの例
|
|
洗練されているけれども親しみやすい
|
デザインから受ける印象
|
|
仕事ができる人が使っていそう
|
商品のイメージ
|
|
外出先にもっていくと楽しそう
|
商品の利用シーン
|
KJ法
KJ法とは、回答の類似性や関連性にもとづいてグループ化する手法のことです。調査対象者から得た回答一つひとつをカードに書き出し、グループ化していくことで、複雑な情報をシンプルに整理できます。新たな視点や洞察を得たい場合に効果的な手法です。
【KJ法による整理の手順】
1.発言録からピックアップした回答を付箋に記入する
2.類似する発言をグループに分ける
3.各グループの名称を決める
4.グループ同士の類似性や関連性を検証する
5.検証結果を構造化して図などに示す
KA法
KA法とは、「出来事→心の声→価値」の順に発言内容をまとめていく手法のことです。事実と仮説が整理されるため、調査結果から新たなアイデアを導き出したい場合に適しています。
【KA法による整理方法】
|
出来事
(調査対象者の発言に表れている事実)
|
|
心の声
(出来事から推察される心理)
|
価値
(出来事・心の声から導き出される真のニーズ)
|
【具体例】
|
出来事
「出張が続くと運動不足になりがち」
|
|
心の声
「出張先でもワークアウトをしたい」
|
価値
「手軽に持ち歩けるエクササイズグッズ」
|
上位下位関係分析
上位下位関係分析とは、インタビュー内容から重要と思われる項目を抽出し、重要度を比較する手法のことです。発言の重要度や優先度が可視化されるため、分析をスムーズに進めやすくなります。調査対象者の本質的なニーズを導き出したい場合に適した手法です。
【上位下位関係分析による整理方法】
1.「〜がほしい」:行為を実現するための具体物
2.「〜がしたい」:本質的なニーズを満たすための行為
3.「〜になりたい」:本質的なニーズ
まずは具体物に関するキーワードを含む発言をひとつずつカードに記載します。類似する内容のカードをグルーピングし、「行為」が表出しているカードを選出しましょう。さらに、類似する行為が表れているカードをグルーピングし、本質的なニーズを導き出していきます。
定性調査の分析結果レポートを作成する手順
定性調査の結果を分析レポートにまとめる際の手順についてお話します。
1. 分析結果の整理
はじめに、前述の分析手法を用いてデータを整理し、調査結果の概要を把握します。定量調査のように回答が多い/少ない、割合が高い/低いといった判断をすることのないよう、調査対象者から収集した発言を尊重しつつ、全体像や関連性を捉えるのがポイントです。
2. 仮説の検証
次に、調査前に立てた仮説と実際の調査結果との相違点や合致点を確認していきます。とくに、調査前には想定していなかった意外な感想や意見を漏れなく拾い上げていくことが重要です。新たにわかった点を分析結果に取り込み、仮説を客観的に検証しましょう。ここでも担当者の個人的な主観や独自の解釈が混在することのないよう、複数名で検証を進めるのが得策です。
3. 分析結果の検証と結論への集約
他のデータや資料と照らし合わせたり、担当者以外から客観的な意見を聴取したりすることで、分析結果の妥当性を検証します。調査外のデータや意見は、あくまでも参考までに聴取するものです。とくに社内で挙がった意見や見解は同じ組織に属する担当者にとって理解しやすい傾向があります。調査対象者から得た意見や感想よりも、社内の声を優先することのないよう注意しましょう。こうして検証した調査結果を、結論へと集約していきます。
定性調査の結果をまとめる際の注意点
分析結果レポートを作成する際に、注意しておきたいポイントを紹介します。レポートのまとめ方次第では調査の効果が薄れてしまうおそれがあるため、次の3点を十分に考慮しておくことが大切です。
定量的な判断に陥らないようにする
定性調査で重視すべきは質的な情報です。量的な情報に惑わされないよう、十分に注意する必要があります。
たとえば、「調査対象者のうち半数以上が『また購入したい』と回答している」「よって、当面は商品を改善する必要はない」といった結論の導き方は、定量的な判断に偏っています。むしろ、「次回は購入しないつもり」「迷っている」と回答した少数の調査対象者がどのような点に不満や懸念を感じているのか、質的な情報に目を向けるべきでしょう。定性調査の目的に立ち返り、定量的な判断に陥らないよう意識することが大切です。
調査目的に沿って検証する
調査結果を分析・検証する際には、調査目的に沿って進めるのがポイントです。調査対象者の声を尊重することは重要ですが、調査目的から外れた意見や感想が羅列されていると、まとまりに欠けたレポートになるおそれがあります。
定性調査では、事前に立てた仮説とは関連の薄い知見を得られるケースも少なくありません。こうした声はレポートの本題には含めず、少数意見として別途まとめるなどの工夫が必要です。
サマリーレポートとフルレポートを作成する
分析結果レポートは、サマリーレポートとフルレポートの2種類を作成することをおすすめします。サマリーサポートは調査結果の概要を簡潔にまとめたもの、フルレポートは調査結果を詳細に示したものです。レポートを閲覧・活用する目的に応じて、両者を使い分けられるようにしておくことが大切です。
たとえば、経営層やマネジメント層への報告には、調査結果の傾向や得られた知見を短時間で確認できるサマリーレポートが適しています。反対に、調査結果に関する社内ディスカッションや、調査を依頼したクライアント企業への報告ではフルレポートを提示するべきでしょう。
定性調査結果の活用方法

定性調査の結果は、幅広い方面で活用していくことが可能です。想定される4つの活用例を紹介します。
活用例1:マーケティング施策の改善
ひとつめはマーケティング施策への活用です。商品の強みや弱点、ユーザーが満足している点や不満を感じている点、具体的な利用シーン、ユーザーのインサイトといった分析結果を、マーケティング施策に反映させます。これにより、顧客心理を捉えた施策を講じやすくなるでしょう。
一例として、キャッチコピーを考案する際には定性調査の結果が役立ちます。ユーザーが利便性を実感している点や、購入の動機となりやすい点を盛り込むことで、消費者に響くキャッチコピーのアイデアを得られるからです。
活用例2:商品企画・開発
新商品の企画・開発や、既存商品の改善に定性調査の結果を役立てる方法もあります。調査対象者が挙げた商品の良い点を新たに開発する商品にも盛り込むことで、顧客ニーズに合った商品を開発できる確率が高まるでしょう。もしくは、既存商品に不満を感じている点を丁寧に拾い上げ、改善を重ねていくことによって売り上げをさらに伸ばせる可能性もあります。企業側が想定していなかった意外な利用シーンや使い方を参考に、同一商品を別の用途で販売したところ、ヒット商品となるケースも少なくありません。
活用例3:ユーザーボイスコンテンツ
ユーザーボイスコンテンツとは、「お客様の声」を伝えるコンテンツのことです。Webサイトや商品カタログ、プレゼン資料などにユーザーボイスコンテンツを掲載することにより、ユーザーの声を通じて商品・サービスの特長やメリットを伝えられます。
自社商品の強みや長所を紹介した場合、それらの見解はあくまでも提供企業側の主観に過ぎないと捉えられがちです。ユーザーボイスコンテンツを併用することで、第三者の影響力が上乗せされる効果が期待できます。ユーザーの声は客観性の高い評価として認知されやすく、商品・サービスの購入を後押しする大きな要因となることもめずらしくありません。
活用例4:ホワイトペーパー
定性調査を通じて得られたユーザーの声を、ホワイトペーパーに掲載する方法もあります。ホワイトペーパーとは、自社の知見やノウハウ、商品・サービスの活用事例などをまとめた資料のことです。ユーザーが情報収集の一環としてダウンロードする際に、担当者のメールアドレスなどを入力してもらい、リード獲得や見込み客の育成につなげる施策が想定されます。また、コーポレートブランディングを強化したい場合にも、自社の知見や実績を掲載したホワイトペーパーが役立つでしょう。
ホワイトペーパーを通じて提供される情報は、基本的には提供企業の見解にもとづいています。より客観性が高く信頼できる情報を提供するために、公的機関が公表しているデータや統計情報などを引用するケースが少なくありません。こうした客観性を担保する情報のひとつとして、定性調査の結果が活用できる可能性があります。
定性調査の結果を効果的に活用するには調査実施後の処理が重要
定性調査は対象者のインサイトを深堀する調査として効果的です。一方で、調査結果のまとめ方によっては重要な意見が埋もれてしまったり、分析結果が正確に伝わらなかったりする原因にもなりかねません。今回紹介した分析手法やレポートの作成手順、まとめる際の注意点を参考に、定性調査の効果を引き出す分析結果レポートを作成しましょう。
ネオマーケティングでは、定性調査の企画・実施にとどまらず、事後の分析やレポート作成まで一貫して対応しています。定性調査を効果的に実施するとともに、的確で見やすいレポートを作成したい事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。