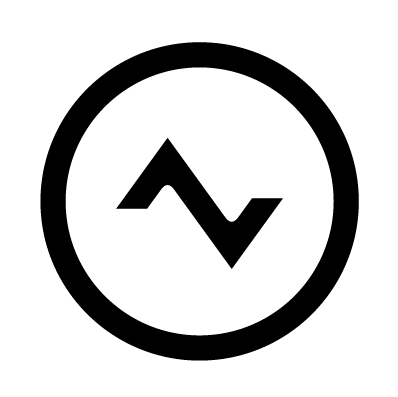市場調査や商品の開発・改善に際して、定性調査の実施を検討している事業者様は多いのではないでしょうか。定性調査にはさまざまな手法がありますが、中でも代表的な調査方法として広く活用されているのが「グループインタビュー」と「デプスインタビュー」です。
この記事では、グループインタビューとデプスインタビューがそれぞれ適しているケースや、効果的に質問をするコツをわかりやすく紹介しています。
定性調査とは
定性調査とは、数値では表せない情報を収集するための調査手法のことです。対象者の価値観や考え方、行動背景などを深掘りし、インサイトを把握したい場合に用いられます。
これに対して、数値で表される情報を収集する調査手法を定量調査といいます。全体の傾向を大まかに把握したい場合や、できるだけ多くの回答を得たい場合などには、定量調査が適しているでしょう。定性調査と定量調査の違いや使い分け方のほか、両者を組み合わせて活用する方法については、次の記事を参考にしてください。
主な手法
定性調査に用いられるインタビューの形式には、主に次の3種類があります。
●グループインタビュー:複数名の対象者に同時にインタビューを実施する
●デプスインタビュー:対象者と1対1でインタビューを実施する
●オンラインインタビュー:ビデオ会議ツールを活用してインタビューを実施する
グループインタビューとデプスインタビューは同時にインタビューする対象者の人数が異なるだけでなく、調査目的や求める回答によって向き不向きがある点に注意が必要です。
なお、定性調査そのもののメリット・デメリットについては次の記事で解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
グループインタビュー(FGI)とは
グループインタビュー(FGI:Focus Group Interview)とは、4〜6名程度の対象者を同室に集めて実施するインタビュー調査のことです。似た属性の対象者を同じグループにすることで、意見を言いやすくなったり、議論が活性化しやすくなったりする傾向があります。下記はグループを分類する際の目安となる属性の一例です。
・年齢・性別
・家族構成
・趣味や嗜好
・ライフスタイル
・商品・サービスの利用頻度や利用シーン
グループインタビューは複数名に対して同時に調査を実施できるため、効率良く調査を進められる点がメリットです。一方で、健康や金銭といったデリケートなテーマについて調査したい場合は、他の対象者に実情を知られたくない場合もあります。このようなケースでは、次に紹介するデプスインタビューのほうが適しているでしょう。
デプスインタビュー(DI)とは
デプスインタビュー(DI:Depth Interview)とは、対象者と1対1で実施する調査のことです。対象者ひとり当たり30分〜90分程度の時間を確保し、意見や感想をじっくりと聴取します。
調査対象者の反応や発言を軸に、意見や感想を深掘りできることがデプスインタビューの大きなメリットです。たとえば、ある商品を長期間使用し続けている対象者について、商品のどのような点が気に入っているのか、改善してほしい点は何か、といったことについて時間をかけて聴取できます。一方で、一度に調査できる対象者は一名のため、グループインタビューと比べて大人数を対象とした調査を実施しにくい点がデメリットです。
グループインタビューが向いているケース

グループインタビューは、どのような場合に実施するとよいのでしょうか。グループインタビューが向いているケースを紹介します。
直接的な反応(表情やニュアンスなど)を確認したい場合
アンケート調査には表れていない、対象者の生の反応を確認したい場合は、グループインタビューが適しています。対面で調査を行うことで、相手の表情や言葉のニュアンスを感じ取れるからです。
一例として、アンケート調査で「(サービスについて)やや満足」と回答した人がいたとしましょう。「満足」や「非常に満足」に届かない理由は、人によってまちまちです。サービスに対してやや不満に感じた点や改善の要望を詳しく聴取するには、インタビュー調査を通じて直接尋ねるのが得策でしょう。
議論を促したい場合
調査対象者同士の議論や意見交換を求めているのであれば、グループインタビューの形式が適しています。対象者が互いに触発し合うことで満足している点や不満に感じている点が思い出されたり、より深い考察を得られたりする可能性があるからです。
実際、自力ですべての回答を考えるのはハードルが高いと感じる対象者が含まれているケースも少なくありません。他の対象者がいることで安心感が得られたり、自分と同じような感想を抱いていた人がいると知って発言しやすくなったりする効果も期待できます。
プライベートに関するテーマが含まれていない場合
他の対象者に聞かれても問題のないテーマであれば、グループインタビューで効率良く聴取するのが得策でしょう。たとえば、自社の商品・サービスを利用した感想など、対象者自身のプライベートに立ち入る可能性が低いテーマなどが挙げられます。
ただし、商品・サービスの具体的な利用シーンなどを尋ねた際、必然的に生活圏や生活パターンに言及せざるを得ない場合があります。こうしたことを他人に知られたくない人もいる可能性があるため、質問項目を検討する際には注意が必要です。
対象者が比較的幅広い場合
調査対象者に比較的多くの人が該当するテーマであれば、グループインタビューを実施しやすいでしょう。必要な人数を同じ時間帯・場所に集めるには、対象者の母数を一定以上確保しなくてはなりません。
たとえば、日用品など多くの人が利用している商品についての調査はグループインタビュー向きです。反対に、ユーザー数が少ない商品・サービスに関する調査や、特定の趣味嗜好の人のみが対象となるような調査であれば、デプスインタビューを選択したほうがよい場合もあります。
デプスインタビューが向いているケース
次に、デプスインタビューが向いているケースを紹介します。次に挙げる目的や状況に当てはまる場合には、グループインタビューではなくデプスインタビューを選択するのが得策です。
対象者の心理や価値観を深掘りしたい場合
デプスインタビューは対象者と1対1で実施するため、相手の反応や回答内容に合わせて臨機応変に質問内容を設定できます。対象者の意見や考えを深く聴取し、心理や価値観をじっくりと深掘りしたい場合に適した調査手法です。
たとえば、ある商品のデザインに対して肯定的な回答を得た場合、「どのような点が気に入っていますか?」といった質問を追加できます。より詳細かつ具体的な回答を得ることで、商品の優位性や改善が必要な箇所を特定しやすくなるでしょう。
新たな視点につながるヒントを得たい場合
企業側が想定していなかった、意外な意見や感想を聴取したい場合にもデプスインタビューが適しています。事前に用意していなかった質問をその場で追加できるため、会話の流れの中で対象者の回答に応じて質問内容を柔軟に変えられるからです。
たとえば、想定外の利用シーンを答えた対象者がいた場合、なぜそのシーンで商品を使っているのか、どのような使い方をしているのか、といったことを深掘りできます。こうした情報が、商品の開発や改善につながる重要なヒントとなるケースも少なくありません。
多くのサンプル数を必要としない場合
デプスインタビューは一人ひとりの対象者から回答を聴取するため、調査の効率としてはグループインタビューよりも劣ります。したがって、サンプル数の多さよりも聴取内容の深さや詳しさを重視したい場合に適している調査手法です。
一例として、商品を購入した際の詳細な状況をヒアリングしたい場合、回答数の多さや回答のバリエーションの豊富さよりも、できる限り具体的な状況を聞き取ることのほうが重要です。このように、量よりも質を求めることが調査の目的であれば、デプスインタビューを選択するのが得策でしょう。
デリケートな話題が含まれる場合
健康状態や金銭関係、家庭内の事情など、デリケートな話題が含まれる調査はデプスインタビュー向きといえます。対象者と1対1で実施するため、プライバシーを保護しつつ調査を進められるからです。
こうしたテーマに関する調査を実施する際には、調査会場の環境にも配慮する必要があります。1対1でインタビューを実施していたとしても、会話の内容が周囲に聞こえているようではあまり意味がありません。会話の内容が漏れることのないよう、扉を閉められる部屋などを確保する必要があります。
効果的に質問をするコツ
定性調査を効果的に進めるための質問の仕方を紹介します。対象者の本音を引き出せるよう、次に挙げる3点を意識することが大切です。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分ける
Yes/Noの二択など、容易に答えられるクローズドクエスチョンと、自由回答形式のオープンクエスチョンを適宜使い分けましょう。一般的には、クローズドクエスチョンのあとで、なぜそう感じるのか、といったオープンクエスチョンを投げかけると効果的です。
たとえば、「(商品について)どう思いますか?」という質問は漠然としているため、対象者は何を答えればよいのか迷ってしまう可能性があります。まずは「商品を身近な方にすすめたいですか?」といったYes/Noで答えられる質問を投げかけ、その上で「なぜそう感じるのですか?」「どのような点をすすめたい/すすめたくないのですか?」といった質問によってインサイトを深掘りしていくとよいでしょう。
バイアスがかかりにくい質問の仕方を意識する
特定の回答を誘導しかねないような質問の仕方を避けることも重要なポイントです。対象者の回答にバイアス(先入観)が影響することで、結果として誘導質問にならないよう注意する必要があります。
悪い例:「価格面では安いと感じる方が多いようですが、価格設定は適切だと思いますか?」
良い例:「価格設定は適切だと思いますか?」
悪い例の場合、あえて「高いと感じる」とは答えにくい雰囲気になりがちです。このように、対象者の本音を引き出す上で必要のない事前情報を提供しないよう、十分に配慮することが大切です。
5W1Hを活用する
定性調査の質問項目は、5W1H(いつ・誰が・何を・どこで・なぜ・どのように)を意識して構成することが大切です。これらの要素を順に尋ねていくことで、必要な情報を漏れなく収集しやすくなります。
とくにデプスインタビューでは、対象者との自然な会話の流れの中で回答を引き出していくことになります。質問者側が常に5W1Hを意識し、すでに得た情報と追加で尋ねる必要がある情報を整理しながらインタビューを進めるのがポイントです。
定性調査の設問例
定性調査に活用できる設問例を紹介します。調査票に具体的な質問の仕方を記載しておくことで、担当者によって質問の内容やニュアンスにばらつきが生じるのを防ぎましょう。
製品・サービスに関する満足度を聞くための設問
調査対象の製品・サービスについて、どの程度満足しているのかを尋ねるための設問例です。
「(製品名)の効果は期待どおりでしたか?」
「どのような点がとくに気に入っていますか?」
「どのような点が想像と違っていましたか?」
はじめにクローズドクエスチョンで大まかな印象を聞き取り、その上でより詳細な感想を深掘りしていくのがコツです。「わからない」「何ともいえない」といった回答にならないよう、対象者が答えた内容に対して詳しく尋ねていくとよいでしょう。
生活習慣や価値観を理解するための質問
対象者への理解を深めるための設問例です。できるだけ具体的な状況や心理を引き出せるよう、質問内容を絞る必要があります。「どんな時に使っていますか?」「どう感じますか?」といった漠然とした質問にならないように注意しましょう。
「一日のうち、どの時間帯に使用することが多いですか?」
「何をする前/後に製品を利用したいと感じますか?」
「サービスの利用を通じて改善されたと感じるのは、どういった点ですか?」
改善点や新しいアイデアを引き出すための質問
企業側が想定していなかったアイデアや、見落としていた改善点を引き出すための設問例です。対象者が自由に答えやすいよう、インタビューの終盤など打ち解けてきたタイミングで質問を投げかけるとよいでしょう。
「こんな機能があったら便利だと感じる点があれば教えてください」
「購入前は予想していなかった使い方をしたことはありますか?」
「製品が意外なところで役立ったのは、どんな場面ですか?」
調査目的に応じてインタビューの手法を効果的に使い分けよう
グループインタビューとデプスインタビューは、定性調査における代表的な調査手法です。両者はそれぞれ向いているシーンが異なるため、調査目的や聴取したい情報の特性に応じて適宜使い分けていく必要があります。今回紹介した具体例を参考に、調査目的の達成につながる手法を適切に選択しましょう。
ネオマーケティングでは、調査の企画・設計から対象者のリクルーティング、インタビュー専用ルームのご用意まで、定性調査に必要なサービスを一気通貫で提供しています。対象者抽出に役立つ事前のWEBアンケート調査や、インタビュー調査の結果を施策に活かすためのワークショップ/デブリーフィングといったサポートにも対応可能です。インタビュー調査の実施を検討中の事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。