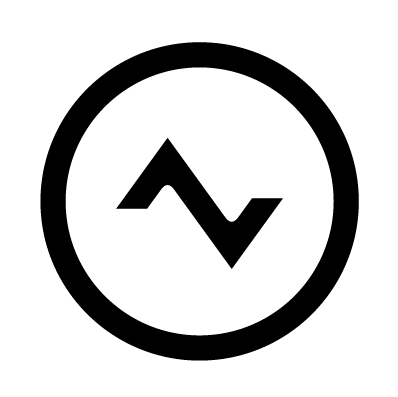マーケティングリサーチは大きく「定性調査」と「定量調査」に分けられます。マーケティング活動に活用するためには、それぞれの特徴や手法を適切に理解しておくことが重要です。
今回は、定性調査の特徴やメリット・デメリット、定量調査との使い分けなどをご紹介します。定性調査と定量調査の使い分け方・組み合わせ方にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。
定性調査とは
定性調査とは、「数値」で表せない情報をリサーチするための調査手法のことです。生活者の心理や行動理由などについて、調査対象者の言葉や行動といった定性的な情報を元に分析します。
たとえば、ある商品を使用した消費者から、「満足している」「やや不満」といった感想を得たとしましょう。具体的にどういった点に満足しているのか、不満を感じたのかについては、より詳細に聞いてみないとわからないケースが多いと考えられます。このように、対象者のインサイト(内面)を深掘りして調査することが定性調査の主な目的です。
定量調査とは
定量調査とは、回答ボリュームや割合が「数値データ」で表される調査手法のことです。回答が多い・割合が高いといった定量的な情報を分析や検証に活用します。定量調査の代表的な手法と主な実施目的は次のとおりです。
【定量調査の主な手法】
・ネットリサーチ
・会場調査
・ホームユーステスト
・郵送調査
【定量調査を実施する目的の例】
|
目的
|
概要
|
|
仮説検証
|
調査目的や課題について「〜ではないか?」という仮説を立てた上で、実態はどうであるのかを確認するための調査。
|
|
実態把握
|
商品・サービスの認知度や利用満足度、自社ブランドのイメージ、競合比較などの実態を捉えるための調査。
|
|
効果検証
|
広告の認知度や購買への影響度を調査し、分析結果を施策に反映させるための調査。
|
定性調査の主な手法
定性調査には多くの手法があり、調査目的や調査対象によって活用される手法はまちまちです。ここでは、よく用いられる5つの手法について紹介します。
デプスインタビュー
インタビュアーと対象者、1対1のインタビュー調査です。最も深掘りができる調査手法だといえます。
グループインタビュー
4~6名を同時にインタビューする調査手法です。個々に対する深掘りはできませんが、一度に複数人への調査が可能なため、目的によってデプスインタビューと使い分けることが有効です。
エスノグラフィー(行動観察調査)
インタビューだけでなく、行動観察や自宅訪問などを通して、言葉以外からも情報を得る調査手法です。対象者がインタビュー調査で話せることは、深さの程度こそあれ、あくまで本人が認識できている範囲にとどまります。エスノグラフィー(行動観察調査)は、人の行動や生活環境に現れる無意識に迫れる調査手法です。
オンラインインタビュー
テレビ会議システムを活用して、オンライン上でインタビュー調査を実施できます。対象者の場所を問わず、インタビューを実施できます。
ワークショップ
インタビュー調査などで得た情報や仮説を元に、事業者側の関係者だけでなく、時には一般の生活者、ユーザーも巻き込んで、さまざまな意見をぶつけあいアイデアを収束させる手法です。
定量調査の調査手法について詳しく知りたい方は、次の記事もぜひ参考にしてください。
定性調査と定量調査の違い
定性調査と定量調査の違いは以下の通りです。
|
比較項目
|
定量調査
|
定性調査
|
|
分析データ
|
数値データ |
・数値化できないデータ
・発言録や行動観察データ
|
|
調査目的
|
・仮説検証
・実態把握
・効果測定
|
・仮説立案
・行動理由や心理の深掘り
|
|
効果検証主な調査手法
|
・ネットリサーチ
・会場調査
・ホームユーステスト
・郵送調査
|
・デプスインタビュー
・グループインタビュー
・オンラインインタビュー
・エスノグラフィー(行動観察調査)
|
分析データの違い
●定量調査:数値データ
●定性調査:数値化できないデータ、発言録や行動観察データ
定量調査で分析するのは数値データです。たとえば「女性20代の●%が購入したいと言っている」などのように、年代や性別など、さまざまなセグメント別に分析できます。
一方、定性調査で分析するのは、インタビューや観察によって得た言葉や行動などの数値化できない情報です。
調査目的の違い
●定量調査:仮説検証、実態把握、効果測定
●定性調査:仮説立案、行動理由や心理の深掘り
定量調査は、仮説の確からしさを数値的に証明したい場合や、市場全体の状況、広告による態度変容などをデータで把握する場合に適しています。数値として全体傾向を把握しやすい点、客観的な根拠として示しやすい点で、仮説検証、実態把握、効果測定の目的で実施されます。
定性調査は、課題を解決するための仮説立案、アイデアのヒントを得るために実施します。定性調査で得た生活者の言葉を分析することで、「生活者のニーズは○○なのでは?」「生活者が感じている価値は○○なのでは?」という仮説を立てられます。
また、生活者の行動理由や心理を深掘りし、生活者のニーズやインサイト理解を行う目的でも実施します。
調査手法の違い
●定量調査:量的なデータを収集
●定性調査:生活者の心理を深く理解
目的の違いに応じて、それぞれの調査手法も異なります。定量調査は、主に選択肢式の質問を用いて量的なデータを収集する手法であり、多くの参加者から回答を得ることに焦点を当てています。対照的に、定性調査は一人ひとりの生活者の心理を深く理解し、アイデアや仮説につなげることを重視しています。
定性調査と定量調査のメリット・デメリット
定量調査・定性調査には、それぞれメリットとデメリットの両面があります。メリット面だけでなく、デメリット面も理解した上で調査目的に合った手法を選ぶことが大切です。
定性調査のメリット
●生活者心理やインサイトを把握できる
●仮説立案に利用できる
●アイデア創出に利用できる
人の行動には、必ず心理的背景や理由があります。定性調査では、意識や感情に迫り、生活者を動かす「インサイト」を探る上で役立ちます。昨今、成熟市場やコト消費といわれるように、品質の良さだけで売れる時代ではなくなりました。一人の生活者を徹底的に深掘りし、インサイトを捉えた価値提供が求められています。デジタル化によってさまざまなデータが収集できるようになりましたが、生活者の心理を深掘りしインサイトに迫れる方法は定性調査だけです。
また、商品やサービスの改善、マーケティング施策の立案にも、さまざまな「仮説」が必要です。生活者理解を深め、価値観や行動の理由、インサイトを把握することで、マーケティング活動に活かせる具体的な仮説を立てられます。
さらに、定性調査ではインタビューや行動観察を通じて、さまざまな意見や情報を収集できます。思いもしなかった発見につながることもあり、それが新たなアイデアの種になります。得られた情報を元に、製品やサービスの改善案や新商品、効果的なマーケティング施策を考案できます。
定性調査のデメリット
●対象者選定の難しさ
●結果分析の難しさ
●少数の意見であり、量的な根拠はない
定性調査では、調査対象者の選定が非常に重要です。深掘りできる情報をそもそも持っていない対象者からは、情報を引き出せません。聞きたい情報を持っているか、対象者の条件に当てはまっているかを調査前に判断するノウハウが必要です。
よくある失敗が、対象者の条件をあいまいに設定してしまう場合です。たとえば、新しい転職サービスを検討しており、「転職検討者」にインタビューするとします。この場合、将来的に転職を考えているだけの人も、転職サイトに登録して2~3回面接を実施している人も「転職検討者」といえます。
このように「転職検討者」という条件設定をしてしまうと、検討度の差をリクルーティングに反映できず、欲しい情報が得られない可能性があります。そのため、対象者条件は細かく設定した上で、条件に合致する人をリクルーティングする必要があるのです。
また、定性調査は言葉や行動を分析対象とするため、調査参加者によって解釈が異なります。そのため、関係者間で調査結果について認識を十分に共有しておくことが大切です。このように、対象者選定と結果分析に関するデメリットを解消するためにも、調査経験とノウハウを有する調査会社の活用も視野に入れておくことをおすすめします。
さらに、定性調査を何百人も対象に行うのはコストの観点から現実的ではありません。定量調査と比べると調査人数はどうしても少なくなるため「一部の生活者の意見に過ぎない」という指摘を受けてしまうこともあり得ます。定性調査は仮説立案や生活者理解を深める目的で実施すると割り切り、量的な検証は定量調査を実施するようにしてください。
定性調査と比較した場合の定量調査のメリット
●結果が数値で示されるため、全体の傾向がわかりやすい
●客観的に分析を進めやすい
定量調査のメリットとして、全体の傾向を単純化して把握しやすい点が挙げられます。調査結果は数値で把握することになるため、「多い/少ない」「割合が高い/低い」といったデータの特徴を素早く把握できるからです。
また、調査結果の分析を進める際に、数値化されたデータは扱いやすいというメリットもあります。調査結果を表やグラフにまとめて可視化したり、GT表やクロス集計といった分析手法を用いたりすれば、意思決定者や関係者にも共有しやすいでしょう。
定性調査と比較した場合の定量調査のデメリット
●データ分析の知識やスキルが必要
●事前に用意した質問への回答しか得られない
●行動理由や心理の深掘りには限界がある
定量調査を通じて得られたデータを有効活用するには、相応の知識やスキルが必要です。データを偏りなく解釈するには、どのような分析結果が必要かを調査目的や課題から逆算してイメージし、適切な分析手法を選択しなくてはなりません。
また、定量調査では事前に用意した質問と選択肢に沿って回答してもらうのが一般的です。対象者ごとに追加の質問を設けられないため、回答の背後にあるインサイトを深掘りするのは容易ではありません。インサイトを深く調査したい場合は、定性調査と適宜組み合わせるなど対策を講じておく必要があります。
定性調査と定量調査の使い分け方
定性調査は対象者のインサイトを深掘りできるため、次のような課題に対する調査手法として適しています。
【定性調査が適しているケース】
●商品・サービスのターゲット像を明確にしたい場合
●改善点を具体的に把握したい場合
●生活者の生の声や意見・感想を収集したい場合
一方、次のような課題に対しては、定量調査のほうが適していると考えられます。
【定量調査が適しているケース】
●全体の傾向を知りたい場合
●商品やサービスの評判などを比較したい場合
●客観的なデータを用いて証明したい場合
たとえば、ある商品を実際に使ったことがあるか、といった事実を確認したいのであれば、定量調査を通じてデータを収集可能です。これに対して、その商品を使用した感想や、他社商品を使ったときの印象の違いを詳細に聴取したい場合は、定性調査を実施するのが得策でしょう。
定性調査と定量調査の組み合わせ方
ここまでに見てきたとおり、定性調査と定量調査にはそれぞれ向き・不向きがあります。両者のメリットを活かしつつデメリットを補うには、定性調査と定量調査を組み合わせて活用していくのがおすすめです。具体的な組み合わせの例を2つ紹介します。
組み合わせ1:定性調査で仮説を構築し、定量調査で検証する
はじめにインタビュー調査などで生活者への理解を深め、そこで得られた課題解決のアイデアや仮説の確からしさを定量調査で検証する方法です。仮説を立てるだけでなく、検証する段階を踏むことにより、精度の高い意思決定につなげられます。とくに、ターゲットの市場や生活者に対する理解の解像度が低く、効果的な戦略や施策の見当がつかないような場合には、この進め方が適切でしょう。
たとえば、新規事業として「コンディショナー」を販売するなら、まずは既存のコンディショナーに対して消費者がどのような感想を抱いているのかを率直に話してもらうのが得策です。その上で、定性調査の結果を元に自社が参入できそうな領域について仮説を立て、仮説を検証するために定量調査を実施しましょう。「もし〇〇なコンディショナーがあったら、使ってみたいですか?」といった問いをアンケートに設けておくことで、仮説の方向性が適切かどうかを見極めやすくなります。
組み合わせ2:定量調査で全体像を把握し、定性調査で深掘りする
反対に、定量調査を通じて市場の実態を広く浅く把握したのち、特定の条件に当てはまる生活者の家間をさらに深掘りする方法もあります。定量調査から得られた情報だけでは、具体的な施策に落とし込みにくいケースも少なくないからです。市場の実態を理解した上で、より深く生活者を理解したいのであれば、このような調査の進め方が適しています。
たとえば、飲料メーカーが新商品を開発するにあたって現状人気のあるドリンクを調査したい場合には、定量調査を先に実施しておくほうがよいでしょう。調査の結果、若年層に人気のあるドリンクの傾向が明らかになったことを受けて、そのジャンルの商品開発に注力するといったイメージです。なぜそのジャンルに人気が集まっているのか、ターゲットのインサイトを定性調査で深掘りすることで、商品として打ち出すべき特徴や差別化ポイントを絞り込みやすくなります。
定性調査の成功事例
定性調査の成功事例として、2社のケースを紹介します。
【スポーツ用品】インタビュー調査を商品開発とブランド戦略に活用
-
企業名
アシックスジャパン株式会社
-
実施した調査
グループインタビュー、デプスインタビュー
-
目的背景
これまでランニング以外の競技の商品については、調査経験が少なかったといいます。改めてそれらの競技の商品について、顧客理解を深め、マーケティング戦略立案のために調査を行いました。
-
調査結果、活用
調査を実施したことにより、顧客のインサイトやカスタマージャーニーを理解できました。年間のマーケティング計画や、商品のコミュニケーション設計もこれまでの踏襲や感覚的に作成するのではく、顧客のカスタマージャーニーに沿った形で設計できるようになり、売上につながるようになったといいます。
【審美歯科フランチャイズ】インタビュー調査をサービス改善とリブランディングに活用
-
企業
ホワイトエッセンス株式会社
-
手法
デプスインタビュー
-
目的背景
これまでは定量調査を実施していましたが、数値データだけを使ったマーケティング活動に限界を感じていたといいます。顧客の生の声をサービス強化やCRM強化につなげるために、インタビュー調査を継続実施することを決めました。
-
調査結果、活用
優良顧客へのインタビューを重ねることで、担当者たちも理解していなかったホワイトエッセンスの本当の価値、セールスポイントに気づかされたといいます。そこで得た自社の強みをリブランディングに活用し、ブランドミッションも顧客の声を反映させて生み出しました。顧客のサービスへの意見は、その後のサービス改善方針に取り入れ、経営計画にも反映させました。
定性調査を成功させるポイント
定性調査を成功させるために、意識しておきたいポイントを紹介します。
調査目的を整理し関係者で共有する
まずは調査を行う目的を明確にすること、さらに関係者間で共有しておくことが重要です。定性調査で得たいこと、調査目的を明確にしなければ、選定する調査対象者やインタビュー内容もずれてしまいます。
人によって解釈が異なる情報を分析するからこそ、調査目的を関係者間で共有し、インタビュー内容や活用方法について認識齟齬がないよう、事前に確認しておきましょう。
適切な対象者を選定する
定性調査では、「何を聞くか?」より「誰に聞くか?」が重要です。意見の深掘りが可能な人を調査対象として選ぶ必要があります。対象者の選定(スクリーニング)は注意して行ってください。
インタビューフローを作成する
質問内容、時間配分をまとめたインタビューフローは必ず用意し、関係者間でも質問内容に抜け漏れがないか、確認をとっておきましょう。
関係者全員で参加する
定性調査当日は、できるだけ関係者全員で参加しましょう。生の声をその場で聞くのと、調査結果をまとめたレポートを見るだけでは、得られる情報量、生活者理解の深さと幅に大きな差があります。
インタビューは臨機応変に行う
作成したインタビューフローはあくまで参考として捉え、それに縛られる必要はありません。むしろインタビュアーには、その時その時の対象者のコメントを深掘りする姿勢が求められます。決して一問一答のようなインタビューにならないよう、臨機応変に対応しましょう。
インタビュー後はすぐにワークショップを行う
インタビュー後は、すぐに参加者で認識を共有する場を設けましょう。定量調査とは違い、定性調査では得られた情報の解釈が人によって異なります。参加者それぞれが抱いた感覚や意見を共有し、議論を深めることが重要です。内容を鮮明に覚えているうちに、次のアクションにまで落とし込めるようなワークショップを行いましょう。
定性調査と定量調査を効果的に組み合わせて実施しよう
定性調査は生活者の行動理由や心理への理解を深めたい場合に適した調査手法です。一方で、定性調査から得られる情報はあくまでも対象者にとっての感想や意見であり、偏っている可能性も否定できません。定量調査を通じて全体の傾向を把握することによって、こうした定性調査の弱点を補える場合もあります。定性調査と定量調査の特性を理解した上で、両者を適切に使い分けたり、組み合わせて活用したりすることによって、調査の効果をいっそう高められるでしょう。定性調査・定量調査の実施を検討している事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。











.jpg?width=150&height=84&name=0080%20(1).jpg)
.jpg?width=150&height=84&name=WES00398%20(1).jpg)