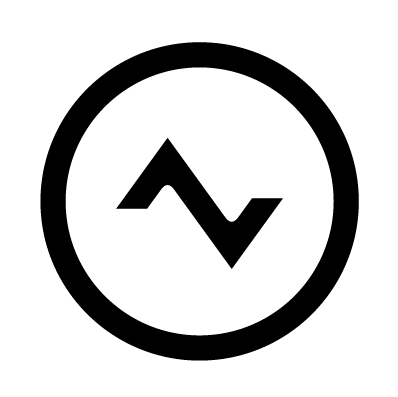大量生産・大量消費の時代が終焉を迎え、世帯におけるスマートフォンの保有割合が約8割*となった現代社会において、顧客の消費傾向はかつてないほどに多様化しています。企業が市場で生き残るためには、ターゲットとする顧客一人ひとりの嗜好性や傾向をより理解し、満足させられる商品・サービスを提供しなければなりません。
この記事ではターゲット・マーケティングとは何か、またターゲット・マーケティングを行うコツとメリットをわかりやすく解説します。
*総務省:令和元年版 情報通信白書 ICTサービスの利用動向, 2020/3/29閲覧
ターゲット・マーケティングとは
ターゲット・マーケティングとは、自社の商品・サービスについて、市場の中でどの層(=ターゲット)を狙うかを定め、その層に集中して販売促進活動を展開していくことをいいます。
「近代マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラーは、マーケティングを単なる販売手段ではなく、需要をコントロールするための社会的・経済的プロセスと捉えています。具体的には、自社の市場をセグメンテーションして適切なターゲットを選択し、そのターゲットの嗜好性、興味・関心や行動を深く調査して理解した上で、ニーズに合った商品・サービスを販売する方針を決定すると述べています。
弊社ネオマーケティングでもターゲット・マーケティングの考えを基に、価値のある商品・サービス提供ができる状態を目指し、顧客のニーズを拾い上げるマーケティングリサーチに取り組んでいます。ネオマーケティングで提供するサービスの特徴をご参照ください。
【参考】フィリップ・コトラー『マーケティング・マネジメント』(丸善出版), 2014
ターゲット・マーケティングを成功へ導く5つのコツ
それでは、コトラーのマーケティング理論を参考に、ターゲット・マーケティングを成功させるためのコツを5つご紹介します。
ターゲット・マーケティングを成功させるコツ
1. STP分析によりターゲットを絞る
2. 「企業の利益<顧客への提供価値」を念頭に4Pを設定する
3. 成長戦略を描くために市場を再定義する
4. 未来を見据えて価値ある情報を取得する
5. 変革(イノベーション)を起こす
1. STP分析によりターゲットを絞る
マーケティング戦略は、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)というSTPの分析ステップを踏みます。STP分析はコトラーが提唱したマーケティング戦略の基礎的なフレームワークの一つです。
・セグメンテーション(Segmentation)
セグメンテーションは市場の細分化を意味しており、ニーズや性質ごとに顧客をいくつかのグループに分け、まずは市場の特徴を大まかに把握します。
・ターゲティング(Targeting)
ターゲティングは、セグメンテーションしたグループのうち、どのグループの顧客を狙うかを定めることを意味しています。競合他社が複数いる環境において、具体的にどの顧客を押さえにいくかを定めることは非常に重要です。自社にとって最も魅力的なグループを見つけ出します。
・ポジショニング(Positioning)
ポジショニングとは、ターゲットに設定した市場における自社の立ち位置を明確にし、強みを活かせる市場を確立させることをいいます。差別化の方針決めにおいては、縦軸と横軸を設定し、競合他社との違いをマッピングする方法が有効です。たとえばビール飲料であれば縦軸に酸味の強弱、横軸に苦味の強弱などを設定します。
2. 「企業の利益<顧客への提供価値」を念頭に4Pを設定する

STP分析をしたら、次は自社の戦略をマーケティング・ミックス(4P)に落とし込みます。4Pはマーケティングにおけるフレームワークの一つで、製品(Product)・価格(Price)・流通チャネル(Place)・販売促進活動(Promotion)の頭文字を取ったものです。STP分析で定義した市場に投下する、具体的な施策の立案を4Pで定めます。
このとき優先すべきは、企業の利益よりも顧客への提供価値であることを念頭に置きましょう。マーケティング活動とは顧客と長きにわたって良好な相互関係を構築することであり、一過性の商品・サービスの販売による利益ではありません。ターゲットとする顧客が価値を感じる、顧客に選ばれる商品・サービスを目指すために大切な考え方となります。
3. 成長戦略を描くために市場を再定義する
STP分析で市場を定義しましたが、市場は常に急速なスピードで変化しています。長期的な成長戦略を描くためには、常に市場を捉え続けることが必要です。たとえば前述のビール飲料でいえば、市場を「ビール業界」と捉えるか、「アルコール飲料」と捉えるか、はたまた「飲料市場」として大きく捉えるかによっても、位置付けは大きく変わります。一つの市場での成功に満足せず、市場を再定義する姿勢がターゲット・マーケティングには求められます。
4. 未来を見据えて価値ある情報を取得する
コトラーは製品中心のマーケティングを行っていたかつての「マーケティング1.0」の時代から、価値主導の「マーケティング3.0」へと変遷し、さらには顧客の精神性を加味する必要のある「マーケティング4.0」へと移り変わったと述べています。つまり顧客は体験や感情を重視するようになり、顧客インサイトを捉えるマーケティング活動が必要になっているのです。
【参考】フィリップ・コトラー『マーケティングの未来と日本』(KADOKAWA), 2017
顧客のインサイトは目に見えるものではなく、情報を企業側から取りに行く必要があります。そのためインタビューやエスノグラフィーといったマーケティングリサーチが現代のマーケティングにおいて重要な意味を持つことがわかります。
5. 変革(イノベーション)を起こす
そして、企業は全社的に変革(イノベーション)を評価し、革新的な考え方をすることが重要であるとコトラーは述べています。イノベーションに成功したアメリカの洗濯機メーカーWhirlpool社は、白物家電市場が飽和状態であった1990年代に、「Gladiator Garageworks」という新サービスを誕生させました。市場に入り込むことで商品のアイデアを育て、「単なる車置き場であったガレージを心地良いワークスペースに変える」というイノベーティブな考え方で新しいビジネスが創出されたのです。
このように競争に勝ち抜くためにも、創造的なアイデアを組織から吸い上げ、育てる仕組みを持つことが企業に求められています。
【参考】ビジネス+IT:フィリップ・コトラー教授が語る、企業のイノベーションを担う6タイプの人材スキル, 2013/11/21
ターゲット・マーケティングの3つのメリット

最後に、ターゲット・マーケティングを実践するメリットを3つご紹介します。
1. 顧客ニーズへ柔軟に対応できる
ターゲットとする顧客を明確に定義付けることにより、顧客のニーズに対してきめ細やかな対応が行えるようになります。これは企業にとっては効率が良く、かつ顧客満足にもつながるメリットと言えます。
2. 競合優位性を構築できる
ターゲットのニーズと自社のポジションが明確になるため、自社の強みを活かし、市場において有利な競争戦略を推進していくことができます。
STP分析の際、顧客をグループ分けなどせず全部を取りに行けば良いのではないか、と感じた方もいるかもしれません。しかしターゲットの設定が広いと、結局のところ誰に何を届けたいのかが不明瞭になりがちで、競合優位性を構築できません。特定の顧客に狙いを定めた商品のほうが、メリットやそこに込めるメッセージ性がよりシャープに顧客に伝わります。
3. 選択と集中によりコストを適正化できる
ターゲットを明確に定めているため、それ以外の顧客に無駄なコストを割かず、本当に関係性を築きたい顧客へコストを集中的に投下することができます。
ターゲット・マーケティングの実施で市場の勝者へ
ターゲット・マーケティングを成功させるためのコツと、実施するメリットについて、コトラーのマーケティング理論を参考にご紹介しました。繰り返しになりますが、企業の収益性のみを考慮するのではなく、顧客のインサイトを正しく捉え、時代の変化に対応していくことが重要であり、それが市場での勝利へと繋がっていくのです。
ネオマーケティングでは、顧客インサイトを捉えるためのネットリサーチを行っています。自社の商品・サービスのターゲットを明確にするサポートをさせていただけますので、顧客の理解に課題を感じている方はリサーチを活用されてみてはいかがでしょうか。ネオマーケティングのネットリサーチはこちらをご参照ください。