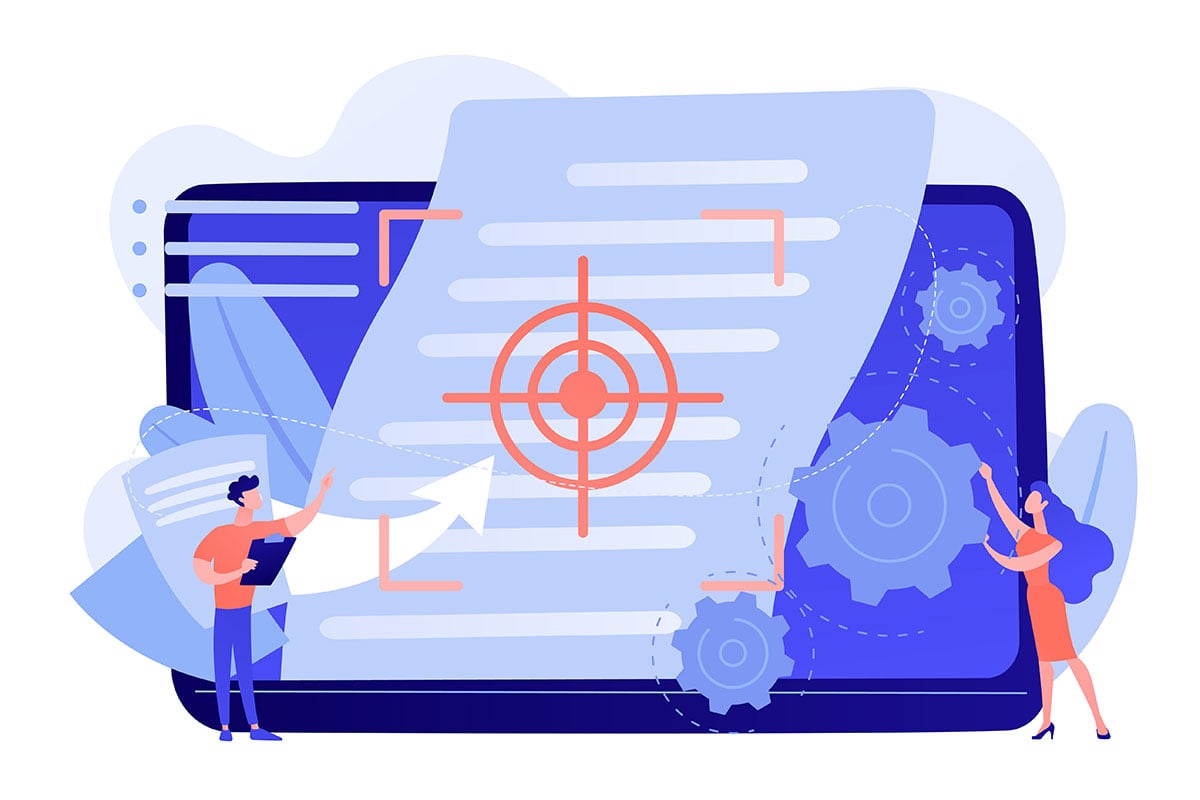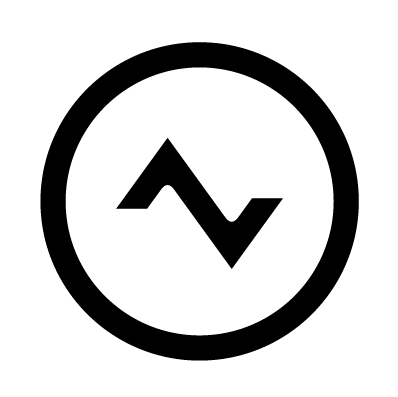マーケティングリサーチには、大きく分けて定量調査と定性調査の2種類があります。このうち、何を知りたい場合に定性調査を実施するのか、目的を把握しておくことは効果的に調査を進める上で非常に重要なポイントです。
今回は、定性調査を実施する目的についてわかりやすく解説します。調査実施時に押さえておきたいコツや、見ておきたいポイントを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
定性調査を実施する目的
そもそも定性調査は何のために実施するのでしょうか。定量調査との違いとともにポイントを整理しておきましょう。
定性調査とは
定性調査とは、調査対象者の感情や行動背景、価値観といった数値化できない「質的な情報」を収集するための調査手法です。代表的な調査手法として、次のものが挙げられます。
・グループインタビュー:複数の対象者へ一度に実施するインタビュー
・デプスインタビュー:1対1で実施するインタビュー
・オンラインインタビュー:ビデオ会議ツールを活用して実施するインタビュー
・エスノグラフィー(行動観察調査):対象者の行動を一定期間にわたり観察する調査
定量調査との違い
定量調査とは、数値や数量といった「量的な情報」を収集するための調査手法です。主な調査手法として、ネットリサーチや会場調査、ホームユーステスト、郵送調査などが挙げられます。回答が多い/少ない、割合が高い/低いといった明確な結果が得られるため、対象者の全体的な傾向を把握したい場合に適した手法です。仮説検証や実態把握、効果測定などを行いたい場合には、定量調査が適しています。
定量調査の結果をより詳細に分析し、対象者のインサイト(内面)を掘り下げたい場合には、定量調査と定性調査を組み合わせて実施するケースも少なくありません。定性調査と定量調査の違いについては、次の記事もぜひ参考にしてください。
定性調査は何のために実施する?
定性調査を実施する主な目的として、次のものが挙げられます。
・消費者インサイトの把握
・新たなニーズの発掘
・商品・サービスの改善点の深堀 など
対象者との対話を通じて、内面や行動の背景を詳細に把握することが、定性調査を実施する大きな目的です。
たとえば、ある商品を「人にすすめる可能性がありますか?」という質問に対して、「ぜひすすめたい」という回答した人の数や割合は、定量調査を通じて把握できます。一方、なぜすすめたいと感じるのか、具体的にどういった点を気に入っているのかを詳細に知りたい場合は、定性調査を実施するのが得策です。
定性調査を実施する際に押さえておきたい3つのコツ
定性調査では、対象者の反応によって臨機応変に質問内容を変え、相手がどう感じているのかを深堀する必要があります。定性調査を効果的に実施するコツを押さえておきましょう。
コツ1:事前に仮説を立てた上で調査を実施する
定性調査の実施に先立ち、自社なりの仮説を立てておくことが大切です。仮説を立てることにより、調査の大きな方向性が定まりやすくなることに加え、収集すべき情報や質問すべき項目が明確になります。
仮説を立てる際にはできるだけ先入観を排し、データにもとづいて考えるのがポイントです。「こうであってほしい」「このように捉えるべきだ」といったように、自社の思いや願望に立脚した仮説を立てることのないよう注意する必要があります。
コツ2:誘導質問にならないように注意する
調査対象者の回答に影響を与えかねない問いかけをしないよう注意しましょう。たとえば、質問する際に「この点については〇〇とおっしゃる方が多いのですが」などと前置きをすると、対象者は無意識のうちに多数派の回答に影響を受ける可能性があります。結果として誘導質問になってしまい、対象者の本音とは異なる回答を引き出すことにもなりかねません。
定性調査では、対象者の率直な意見や本心を引き出すことに意義があります。期待する回答を引き出すための質問にならないよう、尋ねる際の表現やニュアンスにも気を配ることが大切です。
コツ3:定量的な判断に陥らないようにする
定量調査を通じて得られた回答を分析する際には、定量的な判断に陥らないようにしましょう。具体的には、回答が多いものが重要な情報と判断したり、全体うち割合の高い回答を「正しい」意見と見なしたりするのは避ける必要があります。
たとえ少数の意見であっても、新たな視点や着想を得る上で役立つケースは少なくありません。結果レポートにまとめる際にはできるだけ対象者の言葉をそのまま引用し、自社側で独自の解釈を加えないことが大切です。
定性調査で見ておきたい3つのポイント

定性調査を通じて得られる情報は、対象者が発する「言葉」だけではありません。言葉以外にも重要なヒントが隠されている場合があります。定性調査の際に見ておきたいポイントを確認しましょう。
ポイント1:回答者の口調
回答者の声の大きさやトーンといった口調に、興味関心の度合いや感情の高低が表れていることがあります。たとえば、それまでは落ち着いた口調で答えていた対象者が、ある質問を境にいきいきとした口調で話し始めたとしたら、相手にとって興味のある話題と考えられるでしょう。
定性調査では、対象者にとって興味のある話題を掘り下げていくことが重要です。事前に用意した質問票を読み上げるのではなく、相手の反応を見ながら質問内容を臨機応変に判断する必要があります。回答者の口調は、より深く聴取すべき事項を見極める上でも重要なポイントです。
ポイント2:回答者の表情
回答者の表情の変化から、回答の確信度や主張の強さの度合いなどを読み取れることがあります。たとえば、商品のある特徴が話題に挙がった際、それまで真顔で答えていた対象者に笑顔が見られるようになったとしたら、本心からその点を気に入っている可能性が高いでしょう。
こうした回答者の様子を詳細に観察することは、とくにインタビュー調査においては重要なポイントといえます。インタビュアーは質問票や回答のメモに見入ってしまうのではなく、回答者の表情を観察するための余裕をもって調査に臨むことが大切です。
ポイント3:回答者の態度
身を乗り出し気味にして答えるなど、話す/聞く際の態度や姿勢にも対象者の内面が表れていることがあります。多くの人は、興味がある話題を聞くときや、ぜひとも伝えておきたいと感じていることを口にするとき、無意識に身を乗り出しているケースが少なくありません。より深堀するべき回答を見極める際には、こうした回答者の仕草や姿勢が参考になります。
反対に、相手が興味をもっていないことや、あまり気にしていないことを誤って深堀りしないように注意する必要があります。こうしたミスを防ぐためにも、回答者の態度をじっくりと観察することが重要です。
定性調査のコツを押さえて有意義な調査にしよう
定性調査は、消費者インサイトの把握や新たなニーズの発掘、改善点の深堀などが調査目的の場合に効果的な手法です。定性調査を実施する目的を明確に把握するとともに、調査を効果的に実施するコツを押さえることで、より有意義な調査になるでしょう。今回紹介したコツや見るべきポイントを参考に、調査目的のより着実な達成を目指してみてはいかがでしょうか。
ネオマーケティングでは、調査手法に関するご相談に応じているだけでなく、調査の実施から事後の分析、結果レポートの作成まで一貫して対応しています。効果的に定性調査を実施したいとお考えの事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。