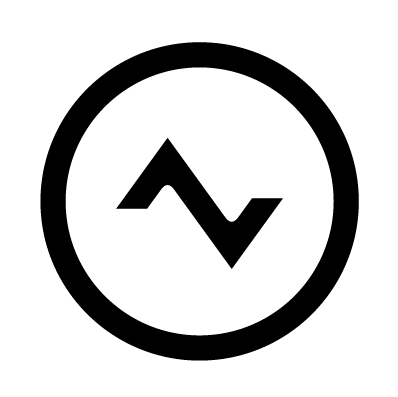定性調査とは、数値では表せない感情や行動背景を深掘りするための調査手法のことです。一口に定性調査といっても、さまざまな調査手法があります。主な調査手法とそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、調査目的に合った手法を選択することが大切です。
この記事では、定性調査の主な種類やよく用いられる「投影法」の手法例についてわかりやすく解説しています。定性調査における対象者のインサイトを引き出す質問例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
定性調査の主な種類
はじめに、定性調査の主な種類を確認しておきましょう。それぞれの手法について、基本的な調査方法とメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
デプスインタビュー
デプスインタビューとは、対象者と1対1で実施するインタビュー調査のことです。対象者の回答に合わせてじっくりと話を掘り下げられることから、インサイトを深掘りしたい場合に適しています。また、健康や金銭といった他人にあまり知られたくないテーマについてインタビューを実施したい場合にも適した手法です。
一方で、一度のインタビューで意見を聴取できる対象者は一人であることから、調査対象者の人数が限られる点がデメリットといえます。
グループインタビュー
グループインタビューとは、複数名の対象者へ同時にインタビューを実施する手法のことです。一度に複数の対象者から意見を聴取できるため、多数の対象者に効率良くインタビューを実施できるメリットがあります。また、属性が近い対象者を同じグループにすることで、他の対象者に触発されて新たな意見が出やすくなったり、意見交換が活発に行われたりするケースも少なくありません。
ただし、テーマによっては本音を話しにくいと感じられたり、一人ひとりの意見を深掘りしにくかったりする点がデメリットです。
エスノグラフィー(行動観察調査)
エスノグラフィーとは、調査対象者の日常生活における行動を観察する調査手法です。特定の商品に関する調査であれば、その商品を日頃どのように使っているのか、どのタイミングで活用しているのか、といった点を調査します。
対象者が無意識に行っている行動の中には、商品やサービスの開発・改善に役立つヒントが隠れているケースも少なくありません。生活者のありのままの様子を調査できる点がエスノグラフィーのメリットです。一方で、比較的長期にわたって調査を実施する必要があることから、調査対象者の人数は限られる傾向があります。
オンラインインタビュー
オンラインインタビューとは、ビデオ会議ツールを活用したインタビュー手法のことです。地理的な条件や会場キャパシティの制約を受けないため、調査を実施する側・調査対象者側の双方にとって負担の少ない調査方法といえます。
ただし、対面で実施するインタビューと比べると、対象者の表情や声のトーンといった非言語情報を把握しにくくなる可能性があります。調査目的によっては、こうした非言語情報に重要な意味があるケースも少なくありません。調査目的や調査のゴールが、オンラインインタビューに適しているか慎重に判断する必要があります。
ワークショップ
ワークショップとは、調査対象者が実際に手を動かしたり、アイデアを出し合ったりする場を設ける調査手法のことです。作業や意見交換を通じて、対象者のインサイトを把握するヒントを得られる可能性があります。
一方で、ワークショップの効果を引き出すには適切なファシリテーションや参加者の選定、空間/環境の整備など、不可欠な要素が複数あります。これらの条件がそろった環境を用意するには、相応のノウハウや経験が求められるでしょう。
定性調査でよく用いられる「投影法」の手法例
ここまでに見てきたとおり、定性調査にはさまざまな種類があります。どの調査方法においても、対象者の意見や考えを深掘し、本音を引き出すことが調査の主な目的です。対象者のインサイトをより的確に導き出すための手法として「投影法」が挙げられます。
投影法とは、調査対象者の潜在意識や無意識下の感覚を可視化・言語化するための手法のことです。投影法の主な手法例を見ていきましょう。
擬人法
調査対象となる商品・サービス・ブランドなどを、人物にたとえてもらう手法です。身近な人やこれまでに出会った人をイメージしてもらうことで、対象者が抱いているイメージを言語化しやすくする効果が期待できます。質問する側としても「人にたとえると、どんな人ですか?」といった簡潔な問いかけによって回答を引き出せる点がメリットです。
コラージュ法
調査対象となる物や事柄を、ビジュアルで表現してもらう手法です。既存のWebサイトや雑誌などのうち、近いイメージのものを挙げてもらうことで、対象者が抱いているイメージを推測しやすくなる効果が期待できます。言語化するのが容易ではない感覚や印象に関しても、視覚的な要素を介して伝えてもらえる点がメリットです。
フォトソーティング
事前に用意した複数の写真から、調査対象となる物や事柄のイメージに近いものを選んでもらう手法です。対象者が抱いている印象を視覚的に伝えてもらえることに加え、なぜその写真を選んだのかを尋ねることで、より詳細なインサイトを聴取できる可能性があります。
第三者投影法
対象者自身ではなく、友人や家族ならどう捉えるのかを問いかける手法です。自分自身が抱いた印象や感じ方を伝えるよりも、第三者がどう感じるのかを想像するほうが話しやすいケースは少なくありません。実際には対象者自身のインサイトが第三者に投影されているため、対象者のインサイトを間接的に引き出せます。
イメージマッピング
調査対象となる物や事柄から連想される語句をできるだけ多く考えてもらい、マッピング図にまとめていく手法です。対象者が発した語句の傾向を分析することで、インサイトを探る手がかりを得られます。
ラダリング
調査対象となる物や事柄が、対象者のどのような価値観に結び付いているのかを深掘りする手法です。
「なぜそう感じるのですか?」「どんな時にそう思うのですか?」といった質問を重ねていくことで、対象者が感じている潜在的な価値に到達できる可能性があります。
【ラダリングによる質問と回答例】
・気に入っている(属性)→どんなところが気に入っていますか?
・リラックスできる(機能)→どんな気持ちになりますか?
・安らかな気持ちで一日を終えられる(情緒)→どんなメリットがありますか?
・前向きな気持ちで仕事に取り組める(価値)
上の例では、「前向きな気持ち」になれることが、対象者が感じている真の価値と判断できます。
文章完成法
空欄の箇所を設けた文を提示し、空欄部分を補ってもらうことにより、対象者のインサイトを探る手法です。
たとえば、「この商品を見ると( )という気持ちになる」といった文を示し、( )の部分に言葉を補うように促します。多くの人は不完全な文章を見ると無意識のうちに言葉を補いたくなるため、より自然な形で対象者のインサイトを引き出せる点がメリットです。
漫画完成法
漫画のコマのうち一部の吹き出しに空欄を設け、対象者に言葉を補ってもらう手法です。
前述の文章完成法に視覚の要素が加わることで、場面や状況をより具体的に想像しやすくなります。特定の利用シーンやタイミングに限定して調査したい場合に適した手法です。
ビジュアル投影法
調査対象となる物や事柄を表現するのに適した写真・イラストなどを、あらかじめ対象者に選んでもらう手法です。調査当日は、なぜそれらの写真やイラストを選んだのか、理由をヒアリングします。商品・サービスやブランドなどに対するイメージを深掘りしたい場合に効果的な手法です。
定性調査の質問例

定性調査は、消費者の深層心理や行動の背景を理解するための有効な手段です。適切な質問設計と注意点を踏まえて実施することで、より深いインサイトを触れることができ、商品開発やマーケティング戦略の精度向上につながります。
調査目的に応じて、以下のような質問を活用することで、対象者の深層心理や行動の背景を探ることができます。
1. 使用状況・実態に関する質問
【質問例】
「この商品をどのような頻度で使用していますか?」
「使用する際の具体的なシーンを教えてください。」
「使用後、どのような気持ちになりますか?」
インタビュー対象者が商品・サービスにどのような価値を見出しているかを聞き出します。
意外な使用頻度やシーンの発見により、従来とは異なるペルソナや新たな市場ニーズに気づけたり、使い方や使用量が適正か、「どこで」「いつ」「誰に」訴求するのが効果的かを導きだすことができます。
2.意識・価値観に関する質問
【質問例】
「この商品に対して、どのようなイメージを持っていますか?」
「この商品がなくなったら、どのように感じますか?」
調査対象となるカテゴリー(例:飲料、化粧品、保険など)に対する「無意識の印象」や「心理的な価値」を深く理解することができます。
インタビュー対象者が何気なく抱いているイメージから、ブランドやカテゴリーの第一想起やポジションが見え、機能的価値と情緒的価値の両面を把握することで、訴求ポイントの見直しに活かすことができます。
3. 購入プロセスや購入理由に関する質問
【質問例】
「購入前にどのような悩みやニーズがありましたか?」
「商品を知ったきっかけは何でしたか?」
「購入の決め手となったポイントは何ですか?」
商品やサービスに対して購入の意思決定プロセス全体を可視化することができます。
マーケティング戦略の見直しや、効果的なタッチポイント設計、プロモーション施策の最適化を図ることができます。
4. パッケージやコンセプトの評価に関する質問
【質問例】
「このパッケージを見た第一印象はどうでしたか?」
「魅力を感じた点とその理由を教えてください。」
「この商品を使いたいと思いますか?」
商品パッケージやコンセプト案に対する「第一印象・共感度・魅力度」などを深掘りし、ターゲット視点の適否や訴求力を評価するインサイトを探ります。
ブランドとターゲットの「認識のズレ」を生まないパッケージデザインやコンセプトの開発に役立てます。
5. インサイト探索に効果的な質問
【質問例】
「この商品を初めて使用した時、どんな気持ちになりましたか?」
「どのようなきっかけでこの商品を使い始めましたか?」
「使用した場所やシチュエーションを教えてください。」
「そのように感じた背景や理由は何ですか?」
感情・要因・場面・背景の4つの要素を意識して質問することで、消費者の深層心理に隠されたニーズやインサイトを探り出します。
質問する際の注意点
効果的なインタビューを行うためには、以下のポイントに注意することが重要です。
オープンクエスチョンで問いかける
対象者が自由に話せるような質問をすることで、より深い情報を引き出すことができます。
良い例:「この商品を使ってみて、どのように感じましたか?」
避けるべき例:「この商品は好きですか?」(はい/いいえで答えられる質問)
「なぜ?」は使わない
「なぜ?」という質問は、対象者に圧迫感を与える可能性があります。代わりに、具体的な状況や感情を尋ねるようにしましょう。
改善例:「この商品を選んだとき、どのようなことを期待しましたか?」
対象者を誘導するような言動は避ける
モデレーターの意見や期待を示すことで、対象者の回答が偏る可能性があります。中立的な立場を保ち、対象者の自由な意見を尊重しましょう。
「先入観を与えるような情報は伝えない」「有益な情報を引き出せそうな対象者にのみ発言させる」「話の展開をコントロールする」といった行動はせず、自然な話の流れに影響を与えないように聞き役に徹しましょう。
回答から導き出せるインサイト
インタビュー調査の回答から通じて得られる情報から、下記のようなインサイトを導きだすことができます。
■潜在的なニーズや動機の把握
感情や行動の背景を探ることで、表面的には見えないニーズや動機を明らかにすることができます。
■商品やサービスの改善点の発見
具体的な使用状況や感想を聞くことで、商品やサービスの改善点を見つける手がかりとなります。
■潜在的なニーズや動機の把握マーケティング戦略の立案
価値観や購買プロセスを理解することで、より効果的なマーケティング戦略を立案することが可能になります。
適切な質問設計と注意点を踏まえて実施することで、より深いインサイト触れ、商品開発やマーケティング戦略の精度向上につながります。
調査目的に合った手法と質問形式を見極めよう
定性調査を効果的に実施するには、調査目的や調査対象に合った手法を選択し、調査対象者のインサイトを引き出すことが重要です。今回紹介した主な調査手法や質問例を参考に、目的の達成につながる定性調査を実施していきましょう。
なお、定性調査には調査方法の選定だけでなく、調査結果を適切に分析・検証するためのノウハウや知識が必須となります。貴重な調査の機会を最大限に活かすためにも、専門的な知見を備えた調査会社に依頼するのが得策です。ネオマーケティングは国内最大級のアンケート会員を保有しており、ご要望に沿った調査方法のご提案や調査実施に対応しています。定性調査の実施を検討中の事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。