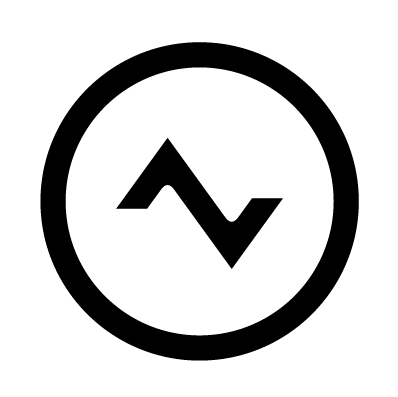今回のマーケティング関連のお薦め本:「ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11」
原著のタイトルは「How Brands Grow」——ブランドの育て方。
本書を推薦するのは、ネオマーケティング執行役員の今泉陽介。「マーケティングの流れを変えた一冊で、マーケター必読の書」について語ります。
推薦図書「ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11」
<今回の推薦図書>
『ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11』(朝日新聞出版)
著:バイロン・シャープ 訳:前平謙二 監修:加藤巧
https://amzn.asia/d/j9t97qM
南オーストラリア大学アレンバーグ・バス研究所のバイロン・シャープ氏がこれまでのマーケティングの常識を検証し、エビデンスをもとに、「11のマーケティングの法則」を提示。「成功したブランドであるほど個性的な連想を持たない」「ブランドの成功と差別化はほとんど関係がない」など、従来の方法論を否定する内容で、刊行当初は賛否分かれて論争が起こったほど話題となりました。
こんな方におすすめ
・マーケティングにかかわるすべての人
・ブランド認知を上げたいけれど、糸口が見つけられない人
この本の紹介者

今泉陽介
メディアインタラクティブ(現:ネオマーケティング)入社後、家電・食品・飲料・日用品・外食・小売等のマーケティングリサーチ企画・設計・実査管理を担当。 2017年にマーケティングソリューションディビジョンにてリサーチからマーケティング施策提案や新サービス開発を行う。
現在のマーケティングトレンドを作った必読書
『ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11』(朝日新聞出版)は世界的に大ヒットしていた本で、2018年に邦訳本が出たタイミングですぐに手にとりました。この本のおもしろさは、マーケティング業界の曖昧で感覚的な領域をエビデンスベースで論証したことにあります。
「STP分析」や「ターゲッティング」、「ロイヤルティマーケティング」など、長く定石とされてきたマーケティングの手法はどこかわかったようでいて “曖昧”としたところがあります。それらを、本書ではデータを踏まえて検証し、それに変わる新たな考え方を一定の方程式のようなものとして提示。エビデンスベースでマーケティング理論を語り、現在のトレンドを作ったという点でも、マーケターにとっては「必読の書」と言えるでしょう。
具体的には「ダブルジョバディの法則」など、11のマーケティングの法則を紹介していますが、論旨は極めてシンプルです。
結局、トップのブランドがロイヤルティも高いし、売り上げも高いし、購買頻度も高い。
「浸透率」が極めて重要で、浸透率を上げる活動を弱小ブランドもやるべき。
言い換えれば、浸透率を高めれば購入頻度とかブランドロイヤルティも高まっていく可能性がある。
シャープ教授が指摘するように「浸透率」に着眼すると、いたずらにターゲットを絞り込んで、小さなパイの争奪戦に参加するという考え方にはなりません。そうではなく、できる限り広いカテゴリーで認知を目指してライトユーザーに定期的にリーチしていくべきで、結果それによりロイヤルティの高い人たちにもリーチすることができます。
私たちは2021年頃から「カテゴリー・エントリー・ポイント(CEP)」のようなパーセプションを起点にした提案を積極的に行っています。カテゴリー・エントリー・ポイントについては、『ブランディングの科学』の続編、『ブランディングの科学:新市場開拓篇』に詳しく登場しますが、「浸透率を高める」ことから考えていくと、カテゴリー・エントリー・ポイントの創造にたどり着きます。
カテゴリー・エントリー・ポイントとは、ブランドを思い出させるきっかけとなる状況や目的のこと。フォロワー・ニッチャー・チャレンジャーブランドがすべきは、トップブランドが持ってないCEPを自分たちで持ち、浸透率を高めていくこと。過剰なターゲティングや差別化に注力するよりも圧倒的に効率がいい。それを本書ではデータから明らかにしています。
『確率思考の戦略論』と『ブランディングの科学』の共通点
「浸透率を高める」という考え方に、マーケティングに関わる多くの方が、実体験を通じて共感されたのではないでしょうか。 そして、この『ブランディングの科学』をきっかけに大きく考え方が変わりました。データの重要性が再確認され、エビデンスベースの話が主流になったのは、この本が分岐点だったのではないでしょうか。
やはり、マーケティングに携わる人は皆、“方程式”のようなものが欲しいのだと思います。たとえば、ベストセラーになっている森岡毅さんの『確率思考の戦略論』(ダイヤモンド社)も需要予測を「NBDモデル」という数式で論証しています。“数式”があることで、施策を進める論拠になるし、周囲を説得しやすい。実践可能な方法論・ノウハウを解説したから『確率思考の戦略論』は大ヒットしたのだと思います。
また、この『確率思考の戦略論』には、USJのブランド戦略が実例として登場しているのですが、それはカテゴリーエントリーポイントの話にもつながります。USJは「映画だけのテーマパーク」から「世界最高のエンターテインメントを集めたセレクトショップ」に変えたことで成功しました。
もともとは「映画が好きな人」をターゲットにしていたUSJですが、「エンターテイメント好き」までターゲットの幅を広げた。『ONE PIECE(ワンピース)』が好きな人も、 『モンハン』や『バイオハザード』のようなゲームファンも対象とした。多様なエントリーポイントを通じて顧客を獲得したことで、V字回復を成し遂げたわけです。
「ブランドはまず市場浸透率を上げてから成長する」(p46)とあるように、ターゲットはできる限り広く考えて、できる限りのパイをとっていくことが大切なのです。その成功実例がUSJでもあるのです。
広告展開で重要なのは、記憶構造の構築から売上へとつなげる“導線“
カテゴリーエントリーポイント(CEP)の考え方は、「同じカテゴリー内でいちばん最初に思い出してもらうポイントを作る」ということです。カテゴリーエントリーポイントを軸にして考えると、広告の考え方も変わるし、実際変わってきているように感じます。かつては、とにかくすぐれたクリエイティブが重要で、それがブランディングにつながると考えられていました。でも今では、そうとも言い切れなくなっています。
私が象徴的だなと思ったのが少し古い事例にはなるのですが、2020年の正月にそごう・西武が出した企業広告「さ、ひっくり返そう。」です。※ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング※木下 勝寿 (著)にも記載されていましたね。
すくっと立っている力士にコピーが添えられる印象的なビジュアルで、記憶にある方も多いかもしれません。そのコピーのメッセージはネガティブで絶望感にあふれていました。でも、それを下の行から読むと、力強いポジティブな決意表明になるという仕掛けでした。
大逆転は、起こりうる。
わたしは、その言葉を信じない。
どうせ奇跡なんて起こらない。
それでも人々は無責任に言うだろう。
小さな者でも大きな相手に立ち向かえ。
誰とも違う発想や工夫を駆使して闘え。
今こそ自分を貫くときだ。
しかし、そんな考え方は馬鹿げている。
非常に印象的で完成度の高いクリイエイティブで当時、大きな話題にもなりました。ただ、ブランドイメージを提示する企業広告とはいえ、この広告を見て、そごう・西武の百貨店に行こうとは思いません。「何かを買いたい」というとき、そごう・西武を選ぶ理由には全くならない広告です。
例えば、「洗練された店員が買いものをサポートする」といったサービスを直球で表現した広告はどうでしょうか。大事な人にプレゼントを買いたい。センスのいいものを選んで喜んでもらいたいけれど何を買えばいいのかわからない。どうしよう…と思ったとき、「あ、そごう・西武だったら助けてもらえる」と思い出してもらえるかもしれません。
こうした、記憶からの“導線“をきちんと考えているかどうかが今、広告展開でとても重要だと感じでいています。
『ブランディングの科学』でも広告についての記述があり、そこではこんなふうに言っています。
「広告の情報が処理されなければ、記憶構造は構築されない。また、広告のブランドに基づいた記憶構造が構築されなければ、売り上げは生まれない。広告の大半がこれら2つの問題を解決できず、広告品が無駄に使われている」(『ブランディングの科学』p199)
広告展開する際も、その商品・ブランドがどのカテゴリーエントリーポイントを取りに行くのかを考える必要があります。その点において、とてもいい広告だなと思うのが、大塚製薬のポカリスウェットのCMです。ダンスをする若者のCMは、「青春」「汗」といったキーワードからポカリスウェットを想起させるし、「ポカリ、飲まなきゃ」のキャッチフレーズで展開しているCMは、母娘のやり取りの中で、「喉の渇き」「水分補給」=ポカリスウェットという記憶を構築しています。
「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」はとてもパワフルな概念で、現在、ブランド戦略のご相談においては、ほとんどのケースでカテゴリーエントリーポイントを活用しています。2番手3番手のブランドは大手の真似をするのではなく、「どこで一番になるか」を考える。トップブランドであってもマーケットを拡大していくには、CEPの概念が欠かせません。『ブランディングの科学』が提示した”エビデンスベースのマーケティング理論”は私自身の中で納得感があった。納得感というよりも、「極めて再現性の高い手法論」だったという表現の方が当てはまるかもしれません。
どんな業界であれ、マーケティングにかかわる人はぜひ、一読しておくべき本だと思います。
今泉陽介に相談する